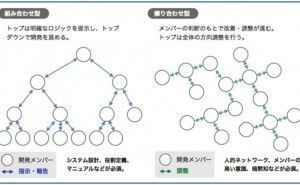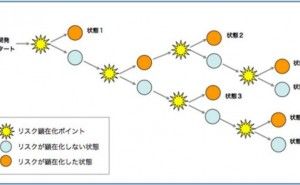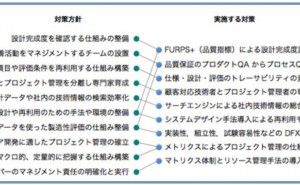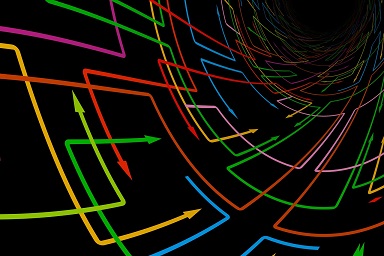
イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。
具体的には、ここまで考えてきた「踏み出すこと・踏み出そうとすることで発生する直接的コスト」×「心理的コスト」の内、心理的コスト(その2):エネルギーをセーブしたいと思う人間の基本心理が存在にどう対処するのが良いのかを考えていきたいと思います。
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その140)へのリンク】
1.イノベーションのための最初の一歩を踏み出すことを妨げる「めんどくささ」
人間はめんどくさがりです。人間のこのような特徴を善意に捉えると、そもそも太古から人間は、常に危険な環境に身を置き、危機に直面した時にその状況に即時に対応できるように、常に備えておかなければならない、ということがあるように思えます。そのため、危機のない状況にあるときには、エネルギーを温存し、危機に備えるということがあり、それが「めんどくさがる」ということとも理解できます。
2.「めんどくささ」を払拭する方法
人間が本来持つめんどくささを払拭し、行動を起こすにはどうしたら良いのでしょうか?それには、私は次の5つがあると思います。
- (1)仕事を細かく分割する
- (2)隣接可能性の効果を信じる
- (3)第一歩を踏み出したことを自分自身でほめる
- (4)時間を掛けても良いと考える
- (5)行動を重視する習慣・カルチャーを作る
では、前回、(1)(2)まで解説しましたので、今回は、(3)からです。
(3)第一歩を踏み出したことをほめる
前回「めんどくささ」を払拭する方法として、「仕事を細かく分割」して、まず第一歩を踏み出す。そうすれば、後から継続して起こる「隣接可能の効果を信じ」て思考・活動すれば良いという議論をしました。つまり、第一歩を踏み出せば、後は極論すると「自然に」当初予想していないような展開が期待できるということです。
しかし、そうであっても、それでもこの第一歩を踏み出すのが気持ち的に難しい。どうしたら良いのか?それは、結果はどうあれ、第一歩を踏み出すという行為そのものを、個人レベルでは自分自身でほめるという習慣を作る、また企業サイドでは、研究者が第一歩を主体的に踏み出したことをほめるという仕組みを作ることが必要ではないかと思います。
後者に関しては、企業においてはやりっぱなしで散らかすだけの人は、評価はされないという価値基準が、特に日本企業においては極めて強いように思えます。もちろん難題に対し、あきらめず根気よく取り組むことは大変重要です。しかし、そのような価値基準が第一歩を踏み出すことを躊躇させ、結果的に面白いアイデアを殺してしまうことにもなることも忘れてはなりません。
(4)時間を掛けても良いと考える
そもそもイノベーションは簡単に生み出せるものではありませんので、短期でいついつまでにこのイノベーションを起こすという目標設定は、その点あまり適正とは言えません。時間を掛けても良いと思えば、様々なことにトライをできますのですし、隣接可能性の効果を利用して、アイデアが発酵し発展することを待つこともできます。ですので、鷹揚に構えて、まずはやってみようと思えるような環境を作れば、最初の一歩を踏み出すハードルも随分下がると思います。
しかし、この点については、切羽詰まらないと良いアイデアがでない、という人がいるのも事実です。エネルギーを集中するには、自分自身を切羽詰まった状況に置くということが必要である。また、特に忙しい人達にとって直前にエネルギーを集中し、良いアイデアが出たという経験は、まさに達成感、さらには快感を感じるもので、そのようなことができる人にとっては習慣になりがちということもあると思います。
一方で、このアプローチの問題点は、このアプローチではアイデアは自分自身の既存の知識のみを基にせざるを得ず、さまざまな他の可能性を試すということができません。この問題点の存在は、あきら...