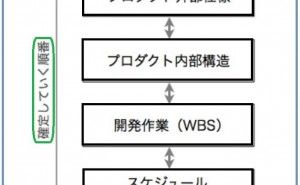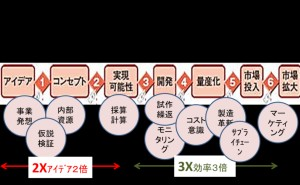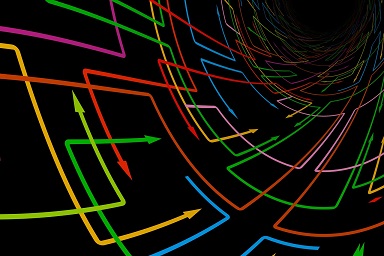
現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための2つ目の要素「同じ一つの行動をするにしても思考の頻度を増やす」さらにはその中の3つの視点の内、最初にあげた分析的に見る(虫の目)の具体的な活動の内の1つ目として「触覚をもって感じる」について解説しています。今回も前回に引き続き「触覚をもって感じる」を解説します。
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その151)へのリンク】
◆関連解説記事 行動を起こすことで得られるのは、情報や経験だけでなく、そのコンテキストや新たな感覚・感情や充実感
7.触覚を使って経験・情報を拡大する方法
触覚を使って、イノベーションのための経験やその結果としての情報を拡大する方法として以下があるのではと思います。
(1)子供のように触る頻度を高める
今もっている触感の記憶の多くは、子供のころ獲得したように思えます。私自身のもっている触感の記憶を思い起こしてみると、たとえば、鉄棒の湿ったざらざらした冷たい感覚、竹箒のつるつるした感触、粘土のねっちり・ねっとりとした感覚、バルサで模型飛行機を作った時のバルサの乾いた感触など、いずれも子供の頃、特に多感で活動的な小学生の頃に得たものです。
つまり、大人になってからは、新たな触感をあまり得ていない証拠と言えます。実際、ホワイトカラーの会社員が、通常の仕事や生活の中で触覚を通して感じる感覚は、極めて限定されているように思えます。触覚を使って経験を増やすには、単純ではありますが、子供のようになんにでも触れてみることで、なにかに触れる機会を多く持つことでしょう。
(2)動物のように手だけでなく、他のからだの部分も使って感じる
友人が猫を飼っているので、猫の行動を観察機会が多くあります。猫は重要な触覚の髭を良く使うのは当然ではありますが、その他からだ全体を飼い主の人間を含め、ものに擦り付けるという行動を良く行います。それを見ていて思ったのは、人間は指先(猫の髭に相当)以外のからだの部分で、物を感じるということはめったにないということです。
しかし、人間のからだじゅうには、指先ほど鋭敏ではありませんが、感触をつかさどるセンサーが存在します。まさに猫やその他の動物がしているように、それらからだ全体の触覚センサーを使わない手はありません。
(3)陶芸家のように触覚をつかって何かを作る
ものづくりにおいて3Dの造形やデジタル技術が活用される世の中ですが、それら新しい技術は大変便利で様々な価値を生み出してくれるものです。また日々の生活における活動でも同じです。たとえばコーヒーを入れる活動にしても、豆を挽き、コーヒーの粉を軽量し・・・という作業をしなくても、コーヒーのカプセルを機器に装着するだけで、おいしいコーヒーを飲むことができる時代です。
しかし、一方で感触を得る機会は、それにより激減してしまうというネガティブな効果もあります。そのため、陶芸家が陶器を作るように、手や指先さらには足(ろくろを回すのに足を使う)など、からだの各部分を多いに使う様々な活動を行うことです。そして必要な活動でも、あえてより原始的なプロセスや道具を使ってやってみることが良いのではないかと思います。
(4)回想家のように経験した感触を頭の中で再現する
人間は日々の生活や仕事の中で、過去に得た感触の経験を思い起こす機会は極めて限定されているように思えます。他の五感の内の4つの感覚にくらべても、大変少ないと思います。
その結果、以前にも解説したように、頭に格納された知識や経験知のスパークでイノベーションが起こるとすると、感触で得た経験は頭の奥底に置かれてしまい、スパークに活...