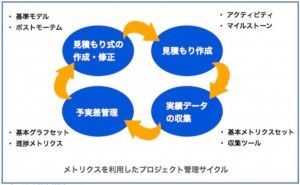これまで五感を一つ一つとりあげ、それぞれの感覚のイノベーション創出における意義と、そこに向けての強化の方法について解説してきました。今回も前回に続けて6つ目の感覚としての「体感」について考えてみたいと思います。今回は「体感で思考する」を解説します。
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その160)へのリンク】
1. 人間は何をもって問題と認識するのか
我々は(とは言いながら私は他人のことは経験していませんので、現実には自分自身のことを考えてみると)、問題を認識する場合、それは頭で考えた結果というより、身体で不快感を感じることで問題を認識しているように思えます。加えて、反対に深刻な問題があると、こころだけでなく、身体まで病んでしまうということは、人間にはしばしば起こることでもあります。
また、日頃の生活や仕事のなかで、問題とまでは認識していなくても、良く分からないのだが「どこかおかしい」と感じることは、良くあることです。その場合、内臓の周辺になんとなくの不快感があり、その不快感が「どこかおかしい」ことを示しているように思えます。まさしく、日本語では「腹落ちしない」という言葉がありますし、英語でも不安や緊張を感じている時の状況を示した言葉として「butterflies in my stomach(胃の中の蝶)」があります。
以上から人間は内臓を含めで、からだ全体で感じ、思考していることがうかがわれます。またそれは、人間が日々の生活の中で問題を避け、解決するという、サバイバルのために、極めて重要な機能として人間(動物?)に与えられたものではないでしょうか。
2. 思考における身体が担う3つの機能
それでは具体的に身体は思考においてどのような機能を担っているのでしょうか。私は、3つの機能があるのではないかと考えます。
(1)五感に加えての6つ目のセンサーとしの機能
一つ目に、五感に加えての6つ目のセンサーとしての機能があるのではないかと思います。振動を身体の一部である筋肉を介して感じる、高温の湿気のある空気をじめじめとしたものとして肌を介して感じる、強風をからだ全体を介して感じるなどです。
(2)六感の統合機能
人間が日々感じる感覚のほとんどは、個別の感覚を認識するのではなく、六感で得られた情報を統合して、統合された感覚として感じているように思えます。たとえば、山奥の清流に手を突っ込むことで、冷たい水の流れを感じるとともに、視覚的にも水の透明度や水面の輝き、さらには周辺の緑の濃さなどを認識する結果、清流というものを統合された感覚として認識しています。
(3)統合感覚を身体全体での快・不快に即座に翻訳し感じる機能
さらにその上で、最後に統合された感覚から、その経験が自分の身体にとって快なのか不快なのかを即座に判断していると思います。この機能は2つのサブ機能から構成されています。
自分のサバイバルを、損なう可能性があるのか、そうでないのか、さらには自分にとって益をもたらすものかを即座に...