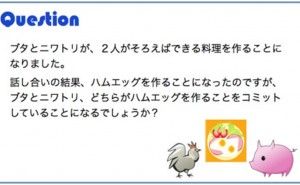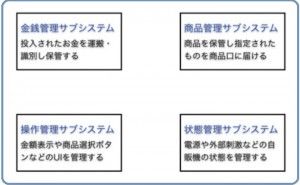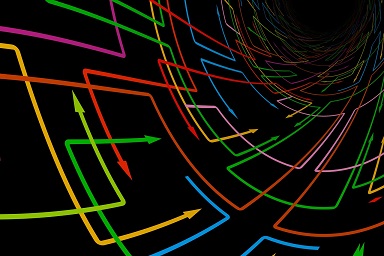
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その134)へのリンク】
失敗の金銭的コストを低減する方法について解説していますが、前回は「時間的余裕を生み出すアプローチ(その1):イノベーションのために時間的余裕を持つという強い意志を持ち実行する」を解説しました。今回は「時間的余裕を生み出すアプローチ(その2):刺激を受ける環境に身を置く」を解説します。
●時間的余裕を生み出すアプローチ(その2):刺激を受ける環境に身を置く
時間を捻出した後にどうするか。時間的余裕ができても、イノベーティブな活動は内的な心理的・知的エネルギーを必要とするため、それだけではイノベーティブな活動を継続することは現実には難しいと思います。そのため、イノベーティブな活動を継続するには、「外的」な刺激のある状況に常に身を置くことが大事ではないでしょうか。
外的な刺激のある状況に身を置くという活動には、もちろんそれなりの心理的・知的なエネルギーは必要ですが、大きなエネルギーではありません。そのような環境において外部からの刺激があれば、それに対応して内的な思考・活動にスイッチが入り、自分が反応せざるを得ません。
【エーザイの「共同化」】
エーザイでは、グローバルの社員1万人全員を対象に、自分の時間の1%を「共同化」とよばれる患者やその家族との接点を持つ活動に費やすということを行っています。そのような場に身を置くことで、単に患者やその家族を知ることができるだけでなく、そこから大きな刺激を受け、また患者や家族と共感をする場が得られるというものです。
そのような刺激や共感はイノベーション創出へのきっかけ、つまり単なる知識や情報の獲得というレベルではなく、イノベーションを創出するための感情面でのインパクトを与えるものです。
社員一人一人が自らこのような場を探し訪問するのは難しいので、エーザイではこのような機会を作る部門として知創部という専門の部署まで用意しています。
【IBMの15%ルール】
IBMにも15%ルールというものがあり、これは研究所(ワトソン研究所)の研究員は、自分の時間の15%を顧客訪問に費やさなければならないというルールです。研究者は目の前のテーマに全身全霊をかけるということになりがちですが、新な次のイノベーティブなテーマを探すためにも、より広い、長期の視点で、外部から刺激を得る場に身を置くことは極めて大事ではないかと思います。IBMでは、ルールとしてこのような活動を研究員に強制しているわけです。
◆個人としてはどうするか
会社という場であれば、このような仕組みや場を会社側が作ってくれます。しかし、個人単位では、このような刺激を受ける場に身を置くという気持ちにするにも、それなりのハードルが存在します。どのようにしたらよいのでしょうか? 2つぐらいの方策が思い付きました。
(1)他の人から提案・誘いがあったらあまり深く考えず、とりあえず乗ってみることを基本ルールとする
他の人から提案や誘いがあると、当然、それは自分にとってメリットがあるのか、ネガティブなことはないのかとあれこれ考えます。しかし、大きなネガティブなことがすぐに思い付いたら話は別ですが、そうでなければ、その提案や誘いにとりあえず乗ってみるということで、刺激を受ける場を増やすということがあると思います。
もちろん途中で中止すべき事象が発生したら、躊躇することなく中止するという姿勢を堅持することは、あわせて必...