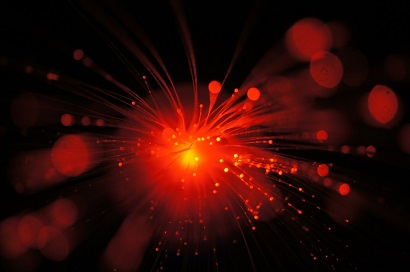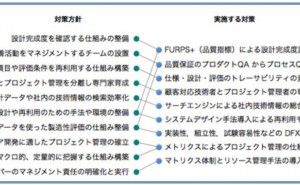前回は思考の構成要素として、「その1:思い付く」と「その2:思い付いたことの発展」があるという話をしました。今回からは「その1:思い付く」には何が必要かについて、議論していきたいと思います。
1. 効率的に「思い付く」ために必要な2つのこと
「思い付く」ためには、何が必要でしょうか?それには、まずは当然のこと知識や経験が必要です。アイデアは何もないところからは生まれません。この部分は、ここまでKETICモデルのK:Knowledge(知識)とE:Experience(経験)でずっと議論をしてきたものです。
この知識と経験だけで、自然発生的に「思い付く」ことはもちろんあるのですが、より効率的に「思い付く」には、加えて思い付きに至るプロセスを促進するための思考のフレームワークが有効です。
2.「思い付く」ための思考のフレームワークの構成要素
更に、「思い付く」ための思考のフレームワークは2つの部分から構成されているように思えます。1つは蓄積した知識や経験から思い付きが起こり易くするための下地を整える「整理するフレームワーク」と、もう1つはそこからの思い付きをより積極的に引き出す、すなわち発想するための「発想のフレームワーク」です。
3. 整理するフレームワーク
整理するフレームワークの基本プロセスは、大きくは2つあります。まず1つ目が、整理する対象の知識や経験を一度分割する作業です。そして2つ目が、その分割した構成要素を何かしらの整理の切り口で再構成するという作業です。もちろん1つ目の作業と2つ目の作業は密接に関係していて、1つ目の分割する作業は当然、2つ目の作業で再構成することを考えて分割します。
したがって、この基本プロセスは、明確に独立して行われるのではなく、現実には行ったり来たりしながら進められることになります。
4. 全体を広く俯瞰的に捉える
この「整理するフレームワーク」で忘れてならない点が、その対象をできるだけ広く捉えて整理することです。一部のみを捉えての整理では、後の「発想のフレームワーク」で、沢山の良...