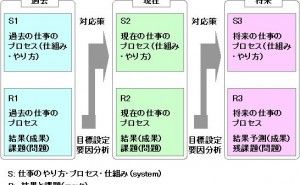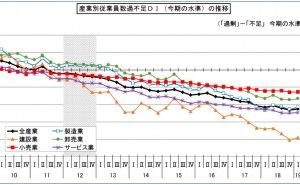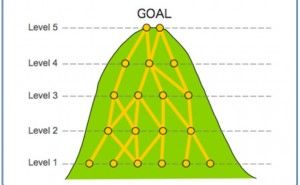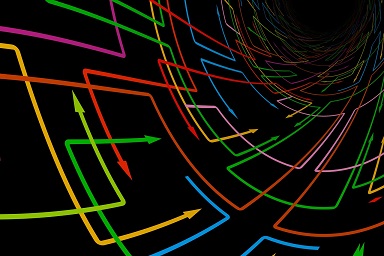
【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その135)へのリンク】
失敗の金銭的コストを低減する方法について解説していますが、前回は「時間的余裕を生み出すアプローチ(その2):刺激を受ける環境に身を置く」を解説しました。今回は「踏み出すこと・踏み出そうとすることで発生する直接的コスト」のなかの心理的コストを解説します。
●「踏み出すこと・踏み出そうとすることで発生する直接的コスト」×「心理的コスト」
これまで、イノベーション創出活動に踏み出すことの金銭的コストと時間的コストについて、それを低減する方策について解説してきました。しかし、コストも問題ではない、また時間もあるという状況の中であっても、それでも人間はイノベーションのための活動に踏み出せないものです。そこに存在するのは心理的な壁です。それをここでは、心理的コストと呼びたいと思います。
心理的コストとは、どのようなものでしょうか?次の2つの心理的コストがあると思います。
〇心理的コスト(その1):やるべきより重要なことが他にもあると考える
金銭的余裕、時間的余裕があっても、やっても良い活動や、やるべき活動は、人間が生き、働く環境の中では、次々に生まれてくるもので、そのような環境の中で、イノベーションに向けての活動に、資金と時間を優先的に配分するということは、現実にはなかなか難しいものです。
〇心理的コスト(その2):エネルギーをセーブしたいと思う人間の基本心理が存在
人間はめんどくさがりです。人間のこのような特徴を善意に捉えると、そもそも太古から人間は、常に危険な環境に身を置き、危機に直面した時にその状況に即時に対応できるように、常に備えておかなければならない、ということがあるように思えます。そのため、危機のない状況にあるときには、エネルギーを温存し、危機に備えるということがあり、それが「めんどくさがる」ということとも理解できます。
●「踏み出すこと・踏み出そうとすることで発生する直接的コスト」×「心理的コスト」への対応策
それでは、これら心理的コストにはどのような対応策があるのでしょうか?
●心理的コスト(その1):「やるべきより重要なことが他にもあると考える」への対応策
次から次へ、やっても良いこと、やるべきことが起こりますので、イノベーションのための活動を優先させるには、イノベーションの重要度の認識を向上させるしか手はありません。それにはどのような方法があるのでしょうか?
〇実は、社内でイノベーションを起こす活動とはどのような活動なのかが、明確になっていない
多くの企業は、イノベーションの重要性を強調しながらも、日々の活動の中でイノベーションの重要性を「常に」伝えるという活動にはあまり熱心にしてきていません。
それはなぜか?実は、イノベーションとはどのような活動なのかを、会社の経営陣やマネジャークラスが、具...