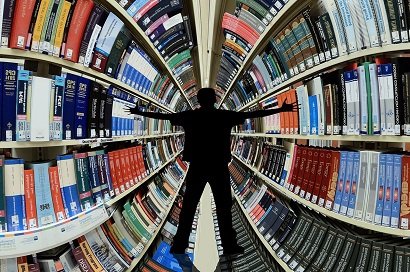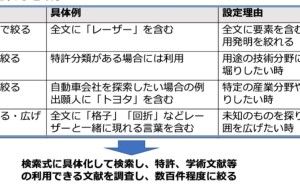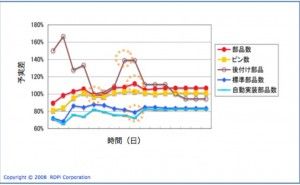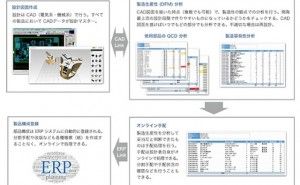前回はエドワード・デシの四段階理論で、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しました。今回も引き続き、本トピックについて解説します。
1、デシが重視する「自律性」
デシはその著書「人を伸ばす力、内発と自律のすすめ」(新曜社)の中で『人には自分の自律性あるいは自己決定の感覚(ド・シャームが自己原因性と呼んだ感覚)を経験したいという生得的な内発的欲求があると思われる』とあります。このことを言い換えるなら、人は自らの行動を外的な要因によって強制されるのではなく自分自身で選んだと感じる必要があるし、行動を始める原因が外部にあるのではなく自分の内部にあると思う必要がある、と解釈できます。
この点に関し、ほとんどの人は自分自身の経験から同意されると思います。私事で恐縮ですが、この自律性の効果が思いのほか大きいなと気づいた事例が2ケ月ほど前にありました。
私は大学院の教員としても活動しておりますが、通常の教育業務以外に学生支援を担当しており、その仕事には院生間の親睦・交流の促進も含まれています。
新型コロナの影響で授業もリモートとなったために、どうしたら院生間の親睦・交流を促進できるかと考えておりました。
そこに、大学院の重要三役のうちの一人の教員から、オンライン飲み会を主催してはどうかという提案があり、子供じみていて恥ずかしいのですが、モチベーションが随分下がったということがあり、またその事実に自分自身驚いたという経験をしました。
その理由は、自律的に主体的に院生間の親睦促進に向け何かしたいと考えていたところ、この場合強制ではないのですが、自律性を損なうような提案が外部からあったということです。
2、もう一つの要素:「有能感」
デシは内発的動機付けに必要なもう一つの要素として、有能感を挙げています。デシは上であげた著書の中で『その仕事をこなす力という感覚は、内発的な満足の重要な側面である。うまくこなせるという感覚はそれ自体が人に満足をもたらす。そして、生涯にわたる職業へ導く最初の力にもなりうる』と述べています。
仕事に打ち込めれば打ち込むほど、いっそうそうした感覚を得ることができることに気づき、いっそう大きな内発的な満足を経験するだろう。と解釈できます。
...