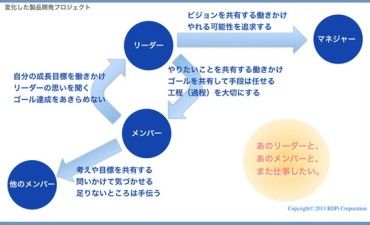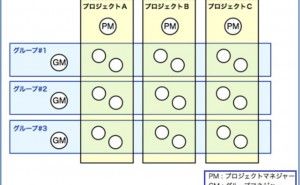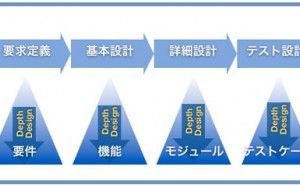前回に引き続き、今回も「切り取った知識の重要部分を発想するフレームワークを使って、イノベーションを発想する」にもとづき、日々の活動の中でどうイノベーションを創出するかについて、解説します。
1.日々の活動の中で「小イノベーション」を量産する
前回解説したように、実際にはシュンペーターのイノベーションのモデルは階層構造になっていて、大きなイノベーション(大イノベーション)が生まれると考えられます。すなわち、日々の小イノベーションの創出・蓄積、さらにそれら間の新結合が重層構造的になされ、さらに小イノベーションが創出・蓄積され、最終的に大イノベーションが起こされるというものです。
したがって、毎日いくつの小イノベーションを創出し、それを蓄積できるかが、将来の大イノベーションの量と質を決めると言って良いと思います。それでは、毎日多くの小イノベーションを創出するにはどうしたら良いのでしょうか。
2.日々様々なもの・ことに関心や興味を持つ
人間というのは、毎日「継続的」にAとBを組合せて C、すなわち小イノベーションを創出するということを「主体的」な意思に基づき行うことは大変困難です。なぜなら「主体的」な強い意志に頼って思考するのでは、エネルギーを消耗してしまい、長続きしません。
それでは小イノベーションを「継続的」に創出するには、どうしたら良いのでしょうか。
人間は、外からの何かの刺激により、頭の中で「!」が付くようなこと(A)を認識すると、脳はそのAと関連しそうな、これまで創出もしくは認識して頭の中もしくはその片隅にある小イノベーションや思い出深い情報を、短時間でスキャンしてBを見つけます。そしてそれらAとBから、小イノベーションを起こすということをやっているのではないかと思います。
すなわち「!」が小イノベーションのきっかけとなります。「!」を頭の中で日々起こせるかが、重要なポイントとなります。
したがって、自分の意思で主体的にAとBを組合せて C、すなわち小イノベーションを創出しようとするのではなく、頭の中で「!」が付くようなきっかけとなる刺激を「外から与えてくれる」環境に身を置くということです。それは、自分自身の内部から自然に湧き上がる「関心」や「興味」を持ち、それを維持することと思います。...