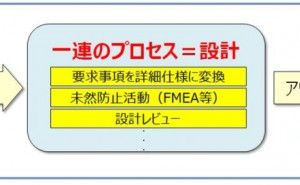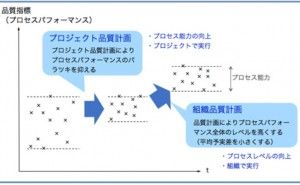今回も「切り取った知識の重要部分を発想するフレームワークを使って、イノベーションを発想する」にもとづき、日々の活動の中でどうイノベーションを創出するかについて、解説します。
1. 前提が変われば結論も変わる
前回は、いつも1+2=3が正しいとはかぎらないという解説をしました。もちろん1と2を足せば答えは3ということ自体は、誰にとっても正しいことです。しかし、そもそも今回の結論を出すために、1と2を前提とするということが正しくない場合もあるからです。
2. ロジックは誰にとってもいつも正しい
今、ロシアのプーチンが、ウクライナを攻めていることが世界的な問題となっています。大きな災禍をもたら戦争を始めたプーチンは狂人である、などの意見も出ています。しかし、私はプーチンは狂人ではないと思います。戦争を起こせば大きな災禍をもたらし、世界各国から大きな非難の対象となるというロジックは、プーチンにも明確に分っている筈です。
しかし、プーチンと西側の人間の思考の違いは、その前提です。プーチンは旧ソ連が持っていた大ロシアの実現が、西側の人間から狂人と言われようと、戦争犯罪人と言われようと、自分の人生にとって極めて重要と考えていることです。しかし、西側の人間にはその重要性は、思考の前提としていません。
ここで重要なことは、ロジックは普遍的なもので、いつも誰にとっても正しいものです。しかし、その前提には大きな相違が生まれやすいということです。つまり結論の正しさを評価する上で、多くの場合、問題はそのロジックではなく、その前提にあるということです。
3. 前提が正しいかを確認する方法は観察が必要
なぜそのロジックではなく、前提に問題があるのでしょうか。それは、ロジックの方は、筋が通らなければロジカルではないということが自分の思考でわかります。しかし、前提の方は、それが正しいかどうかを判別することは、自分の思考のみでは困難であるからです。
たとえば、奈良時代に、日本を構成する大きな島は何かと問われ、明確に蝦夷地、本州、四国、九州であると断言はできなかったと思います。
前提が正しいかどうかを判別するには、そこには必ず観察が必要です。この日本を構成する大きな島の例に関しては、周辺地域を探検して観察しなければなりません。
4. 小イノベーションを起こすには前提を常に問い直せ
しかし、日々の生活の中で、い...