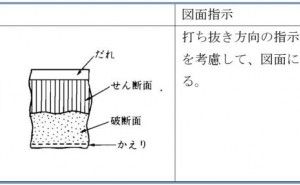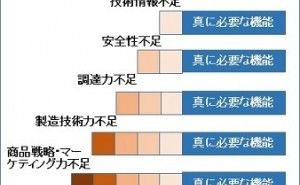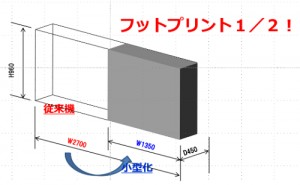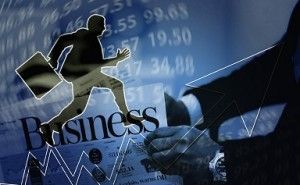1. 苦労して決めた目標、部下がついてこない問題
新規事業・新商品に関わるコンサルティングの現場では、多かれ少なかれ必ずと言っていいほど発生する、「部下がついてこない問題」があります。リーダーがどんなに優秀で実績に優れていても、もしかすると優秀であればあるほどこの問題が発生するように感じます。
特に新規事業・新商品の開発では、複雑で先が読めない状況も相まって、苦労して決めた目標をいざ説明する会を設けても、場がシラーッとしてしまう、熱量が伝わらないなどとご相談を受けます。
また、一見同意しているようにうなずいていても、実際の行動が伴わない・やらないということも多く目にします。このような「部下がついてこない問題」はどのように解決すれば良いのでしょうか?
2. リーダーが伝えるべき、説明するべきは「目標の先」
ここで結論からお伝えします。
リーダーが伝えるべき、説明するべきは「目標の先」です。ビジョンと言うこともありますが、目標を達成した後、どうなるのか?部下はこれが知りたい、納得したいと思っています。
まずは、目標だけを完結に説明するようにしていないかをチェックしてください。
企業における目標はほとんどの場合、Q:品質、C:費用、D:期日で表現され評価指標となっています。既存事業や今までの改善・改良による商品開発では、このような目標でもリーダーと部下の間で認識がある程度合っていて問題とならないケースがほとんどでした。しかし、新規事業・新商品の開発は分かりやすい・誰もが成功すると感じられる目標の立案は非常に難しいことが現実です。
3. 商品開発部門の事例
ここである現場における実際の事例を紹介します。
様々な企業において新商品立ち上げ実績が豊富な商品開発リーダー:Aさん。
商品開発に配属され1年の部下:Bさん。
二人ともなんとかしてこの会社の売り上げをアップする新商品を開発するぞと真面目に取り組んでいました。つまり、「売り上げアップに貢献する新商品を作る」という大きな目標は同じ気持ちでした。であれば、当然うまく進むはず…
ところが実際、部下:Bさんは、リーダー:Aさんから業務を依頼され、受けたにも関わらず進めることが、それ以前に開始することすら出来ませんでした。当然、リーダー:Aさんは何故、部下:Bさんが業務を実施しないのか、他業務で納期に間に合わずとも開始すらしていないことに理解ができませんでした。そこでBさんにこのような問いかけをしました。
- 「Bさん、この業務の目標は何ですか?」
- 「その目標を達成すると、どんなメリットがあるのですか?」
Bさんは目標そのものを答えることができましたが、目標達成後の効果を答えることができませんでした。つまり目標を達成する意義がわからなかったのです。このままでは業務を進めることはできません。この後、目標そのものの意義...