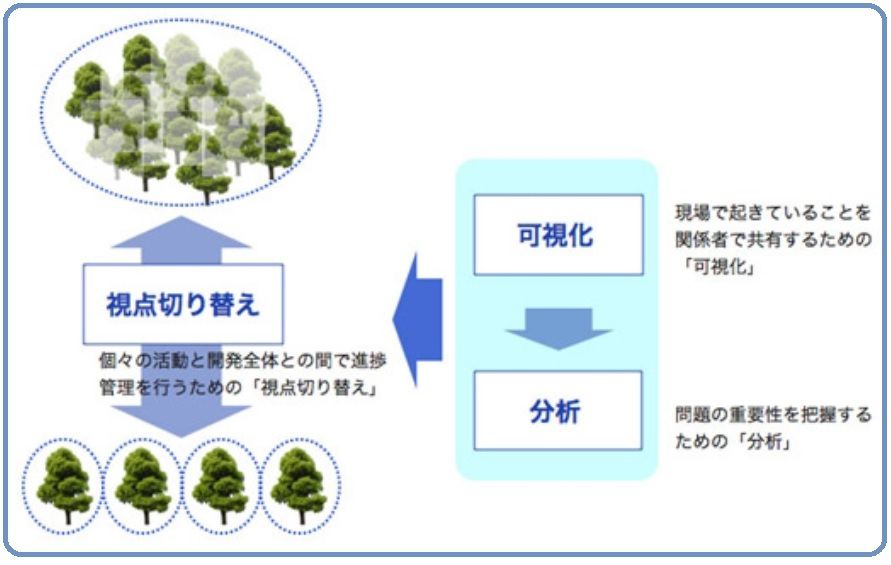
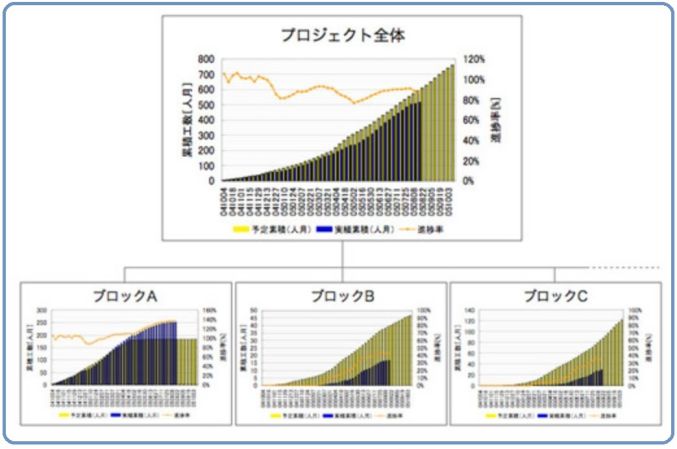
TOP


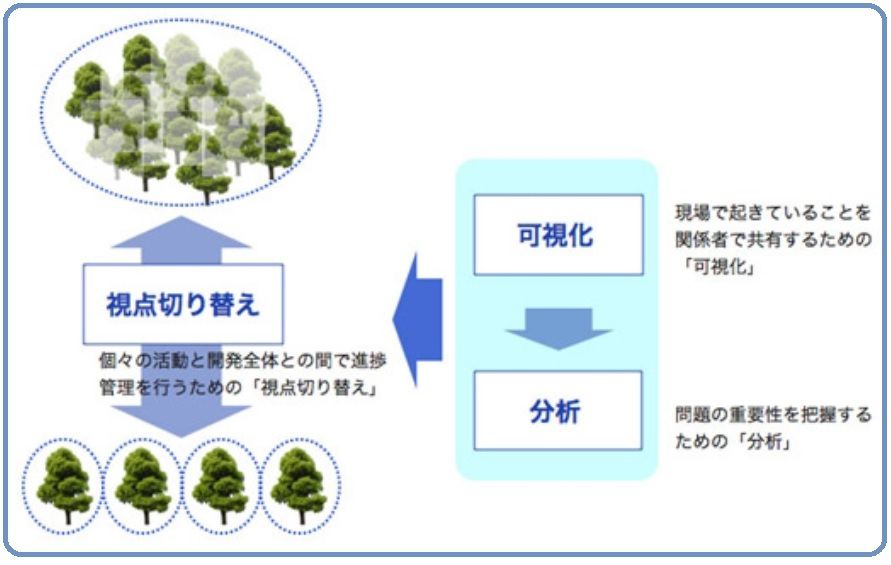
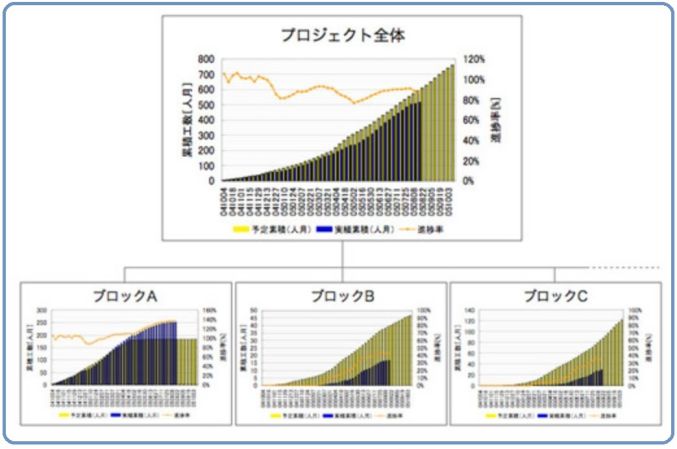
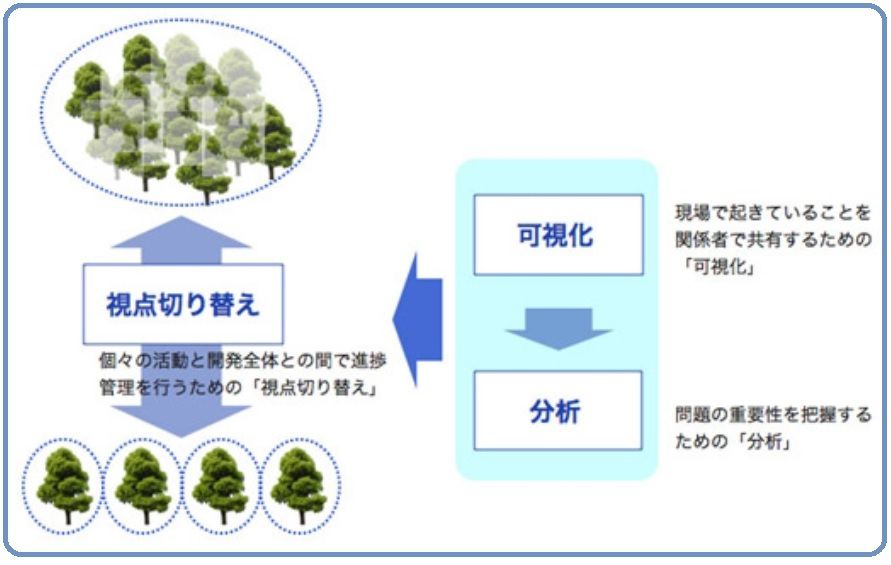
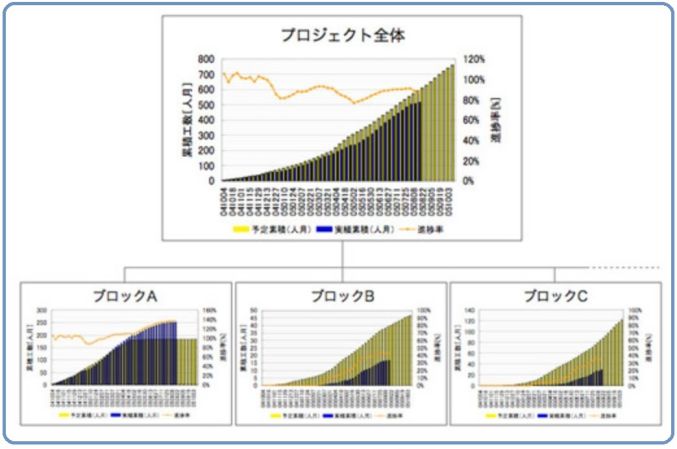
続きを読むには・・・
石橋 良造
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事
現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための1つ目の要素「行動を増やすことで思考を促進す...
現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための1つ目の要素「行動を増やすことで思考を促進す...
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に...
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に...
1. 設計開発部門の悩み 設計・開発部門(以下設計部門)は他部門から様々な要求を受けることが普通です。競争力のある商品...
1. 設計開発部門の悩み 設計・開発部門(以下設計部門)は他部門から様々な要求を受けることが普通です。競争力のある商品...
【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を...
【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を...
「最後の砦、技術力がアブナイ」では、技術者は自律性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを期待されているにもかかわらず、開発現場はそのような技術者に育てる...
「最後の砦、技術力がアブナイ」では、技術者は自律性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを期待されているにもかかわらず、開発現場はそのような技術者に育てる...
前回のその41に続いて解説します。 下図は、改めて操作管理サブシステムだけを抽出したものです。 図78. 操作...
前回のその41に続いて解説します。 下図は、改めて操作管理サブシステムだけを抽出したものです。 図78. 操作...
開催日: 2026-03-13
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



