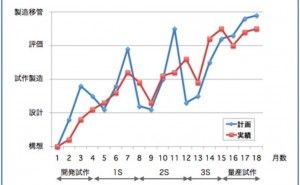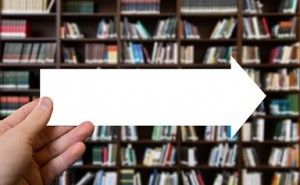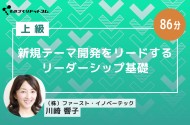みなさんは「傾聴」という単語を耳にしたことが、ありますか?
字で表すとおり、傾聴とは耳を傾けて熱心に聞くこととあります。人材育成や営業研修などで広く一般的に扱われるスキルの一つです。単に「聞こえる」ではなく、相手に集中して「聴く」ことだともいわれます。
さて、今回「傾聴力」について取り上げた背景には、商品企画を行う上でターゲットのニーズが掴(つか)めないという悩みが大きくなってきたことが挙げられます。
衣食住という人間の基本的な欲求が満たされ、さらには仕事や趣味といった社会活動においても、満足とはいかないまでも特に不満を感じない日本では、今すぐ解決したい課題が少なく、ニーズは表面化しにくくなっています。
昨今いわゆるバズった商品は「Pokémon GO」や「あつまれ どうぶつの森」に代表されるゲームのほか、「ウーバーイーツ」や「メルカリ」などのサービスがありますが、あったら楽しい・うれしいものの、極端な言い方をすればなくても死なない、生活する上で必須というものではありません。
このような現代において、ターゲットの潜在ニーズを引き出すことは重要かつ難しい仕事です。潜在ニーズを獲得するためにはいくつかの方法がありますが、最も簡単な方法は傾聴することです。
実際には質問するスキルも必要ですが、顧客インタビューに慣れていないのであれば、まずは傾聴です。
最初にきっかけとして「今、どんなことに興味があるのか?」聞いてみましょう。回答に耳を傾け、疑問に思うことがあれば質問する、これを繰り返します。
話す割合は相手7割、自分3割程度を心掛けるとよいでしょう。傾聴を続けることで、相手が心の奥に抱える「不満」や「不便」に気付くはずです。「気付き」は「仮説」です。仮説をもとに話を膨らませてみることも、潜在ニーズを捉える上で重要な行動となります。
最後に傾聴力を強化するためのコツを一つ紹介します。
「相手がいる方向に体ごと向き、聞くことに集中する」訓練を日常生活で行うことです。実は同僚や家族といった身近な人の話を聞くことが、一番難しいともいわれます。相手の考えを予測できるくらい近しいことはいいのですが、勝手に先読みしたり、聞いていなくても問題ないと思いがちです。
実際に身近な人が満...