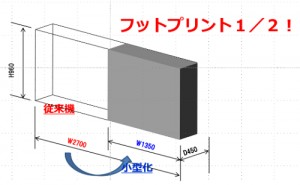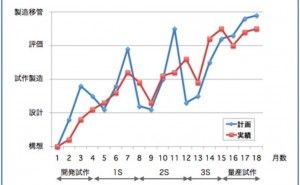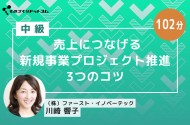【この連載の前回、事業アイディアの企画を後押しする要素、新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その96)へのリンク】
▼さらに深く学ぶなら!
「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!
先日「研究開発部で新規プロジェクトを主導するためのリーダーシップ法」というセミナーを行いました。タイトルにあるように新規事業や新商品の立ち上げを目的に研究開発を行う組織・チームのリーダークラスの方に参加いただくプログラムです。
ご承知のとおり、リーダーシップに関しては、すでに書籍やWeb媒体で数多くのノウハウが公開されています。このような中、どういった課題を持つ方が参加されているかというと、次のような課題がある方が多いようです。
- 新しく新規事業リーダーにアサインされたものの、何から手を付けたらよいか迷っている
- 新規性が高い事業アイディアの出し方と進め方が分からない
- 社内外のステークホルダーとの関係性の構築やリーダーシップに苦労してい...