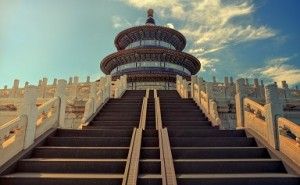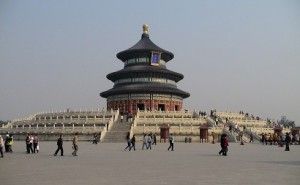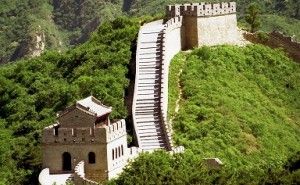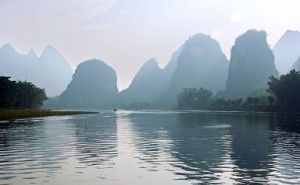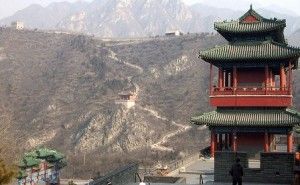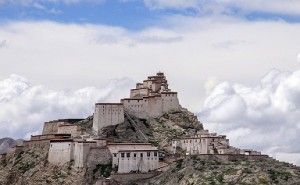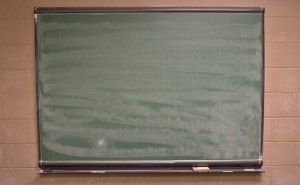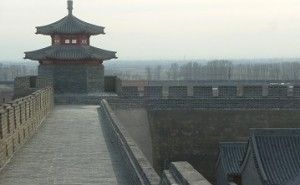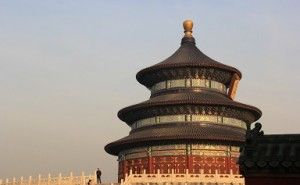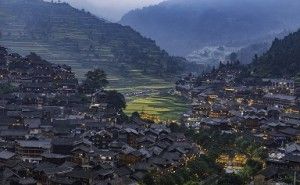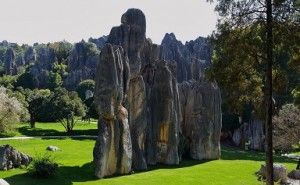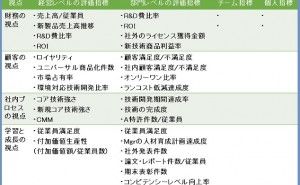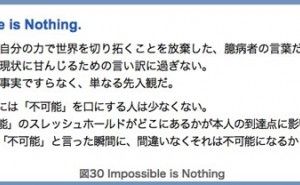【第2章 中国工場の実状を知る】
【作業者について】
中国工場で働いている作業者とは、いったいどんな人だちなのでしょうか。
前回のその7に続いて解説します。
(9)定着させるために何が必要か
中国人が会社への帰属意識が薄いのは確かです。そんな中国人に少しでも自分の会社、自分の工場と思ってもらいたいものです。それが定着につながり品質にもよい影響を与えます。ここでは、作業者の定着に有効な二つの方法を紹介します。
① 自分の仕事に誇りを持たせる
筆者が中国駐在員時代、取引先工場の改善指導をしていたときに、日系工場では見たことはありませんが、香港・台湾・中国系の工場ではあることを見かけました。「作業者が自分は何を作っているのかを知らない」、「自分のやっている作業がいったい何なのかわからない」まま作業をしているという光景でした。香港・台湾・中国系の工場の中には、作業の意味や作っているものが何かなどは作業には関係ないと考えている企業もあり、そうしたことは作業者に伝えていなかったのです。「自分が何をやっているのかわからない」というのは、そこに人としての気持ちや考えは入りませんし、人間としてとても悲しいことです。作業に対するモチベーションは、お金だけと言ってよく、当然品質にも影響があるでしょう。
定着のために作業者に必要なのは、お金以外のモチベーションを持たせることです。
その対応として、自分が作っているものがどのような製品となって世の中に出ていくのかを知ってもらうことはもちろんですが、自分やっている作業の重要性を認識してもらうことが大事です。工場の作業には一つとしていい加減にやっていいものはなく、「あなた(作業者)のやっている作業も品質を確保するために必要な作業」だということをわかってもらうことで、作業に対するモチベーションを持ってもらうのです。
② 満足度を高める(宿舎の設備、おいしい社内食、勉強の場の提供)
作業者に自分の会社と思ってもらうためには、会社に対する満足度を高めることも必要です。満足度は、給料が一番大きな要素ですが、それだけではありません。給料に加えて福利厚生を充実させることも大事です。以前の中国では、作業者が求めていたのは給料、つまりお金だったのです。しかし、最近は単に給料が高いだけでは定着しません。労働環境を整備したり福利厚生も充実させたりしないと定着はおろか応募もなかなか来ません。
福利厚生の内容としては、宿舎の設備、食事などです。普段作業者の人たちは食事にお金をかけないので粗食です。ですから会社で提供する食事は、なるべくおいしいものを出すようにしたいものです。福利厚生でもう一つ筆者お薦めのものがあります。それは、作業者に学習の機会を与えることです。作業者の中には向学心旺盛な人は少なくありません。そうした人たちに勉強する場を提供するのです。日系工場であれば、日本語教室が手軽でお薦めで...