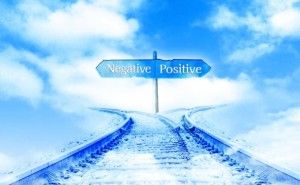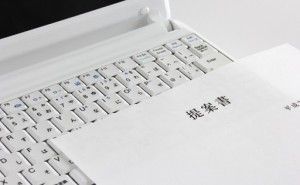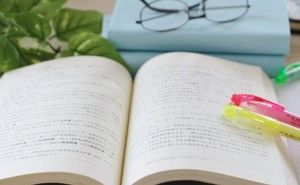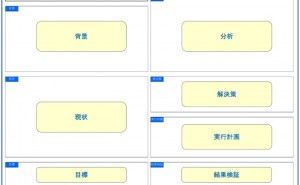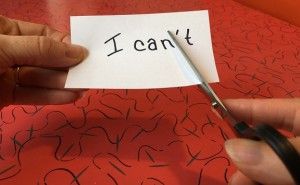前回に引き続き「伝える内容を明確に理解していること」に関する解説です。今回は、技術士第二次試験を通して認識した「伝える内容を明確に理解していること」の重要性です。
【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その32)へのリンク】
1.技術士第二次試験の口頭試験での出来事
技術士第二次試験の口頭試験を受けたときのことです。一人の面接官から「あなたが筆記試験で解答された〇〇について説明してください」という質問がありました。〇〇は専門分野の技術に関する内容です。
そこで、「△△です」と回答しました。このように回答したらすぐに△△に関する質問を受けました。「エッ?」と思いましたが「□□です」と回答しました。連続した質問に困惑しましたが回答できたので安心していました。すると、今度は、□□に関する質問を受けました。「エッ?」と再度思いましたが、「◇◇です」と回答しました。この質問でやっと〇〇に関する一連の質問が終わりました。○○に関しての連続した質問だったので驚きました。
連続した質問を受けたとき、〇〇に関して「理解したつもり」だったら2回目あるいは3回目の質問に回答できなかったと思います。回答できなかったら減点されていたと思います。〇〇について「理解していた(掘り下げて理解していた)」ので3問とも回答できました。
2.「理解したつもり」では説明できない
「技術士第二次試験の口頭試験での出来事」からわかるように「理解したつもり」では質問に対して説明できません。2018年3月13日に掲載した「“理解したつもり”から“理解した”へ」をテーマにした記事の中でも「質問に回答できない場合には理解したつもり」ということを書きました。
自分が「理解している」と思っても実は「理解したつもり」だったのでは人に説明できません。
書き手が「理解したつもり」で書いた技術文書を読み手が読んで「理解した」ということはありません。読み手は「知らない人」だからです(内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その2)参照)。
「伝える内容を明確に理解していること」は、内容が明確に伝わる技術文書を書くうえで重要なことを認識してください。
次回に続きます。...