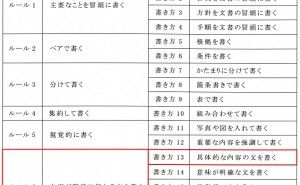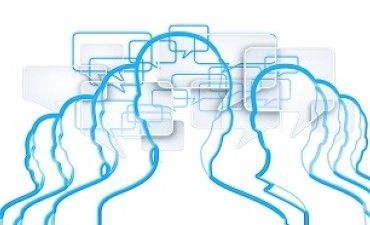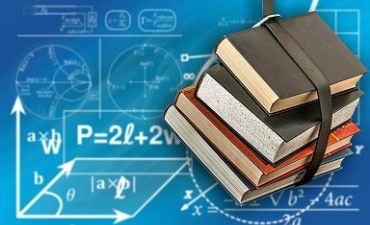▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
1. 感情の良し悪し、あなたの感情を他人はわからない
人は感情をもって生きています。この感情が良い方向に働くことがあれば、足を引っ張ることもあります。楽しいと感じることは高い集中力やモチベーションを発揮して物事を成し遂げることができます。しかし、やらなければならないことでも、つまらない、面倒くさいと言って放棄したら成果はありません。さらにやりたくない言い訳や理由を付け足すと、余計に状況は悪化します。人の集中力も長くは続かないので、良いモチベーションから始めても、次第に低下していきます。モチベーションが低下した時に、再度行動を起こすのにどうしたらよいかです。
怠けている自分との勝負となりますが、何か手を動かしたり、比較的簡単な行動することです。悪い感情に逆らうには、あまり考えずに、機械的に行動しま...