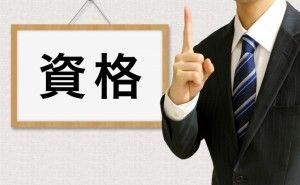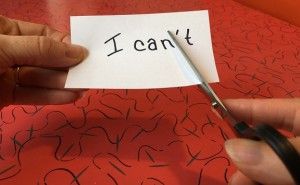▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
1. 正しいこと、正しいことにとらわれ過ぎないことも大事
ほとんどの人が正しいこと、間違っていないことを進んで行うでしょう。そしてその正しいことは経営データ、顧客情報、製品分析など何かを基準にしていることが多いのです。それによって仕事の成果やチャンスが得られることも多いでしょう。しかし、一つの意見があれば、当然それに対する反対意見もあります。適切に対等な状態で議論が進めばよいですが、必ずしもそうとは限りません。片方の意見が正しい、反対意見は悪いこととなってしまいます。
そうすると、自然と分断が進みます。実際のところ、正しい意見の方が良い結果がだせるとしても、反対意見を否定することは別の問題を生みます。反対意見の人はそれなりの考えを持って支持しているので、善悪的、感情的...