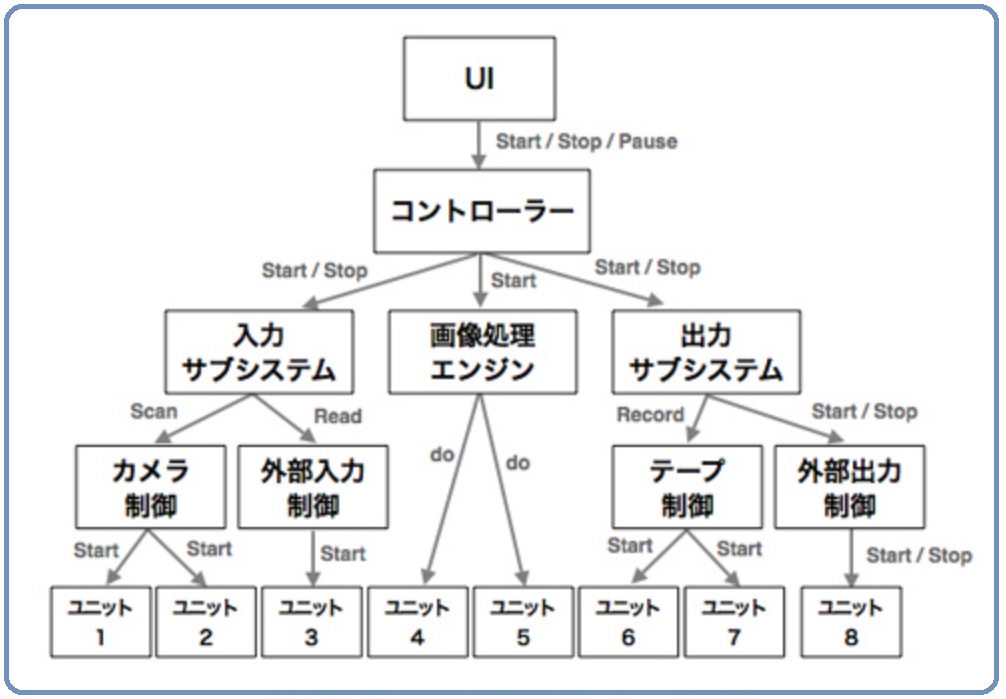
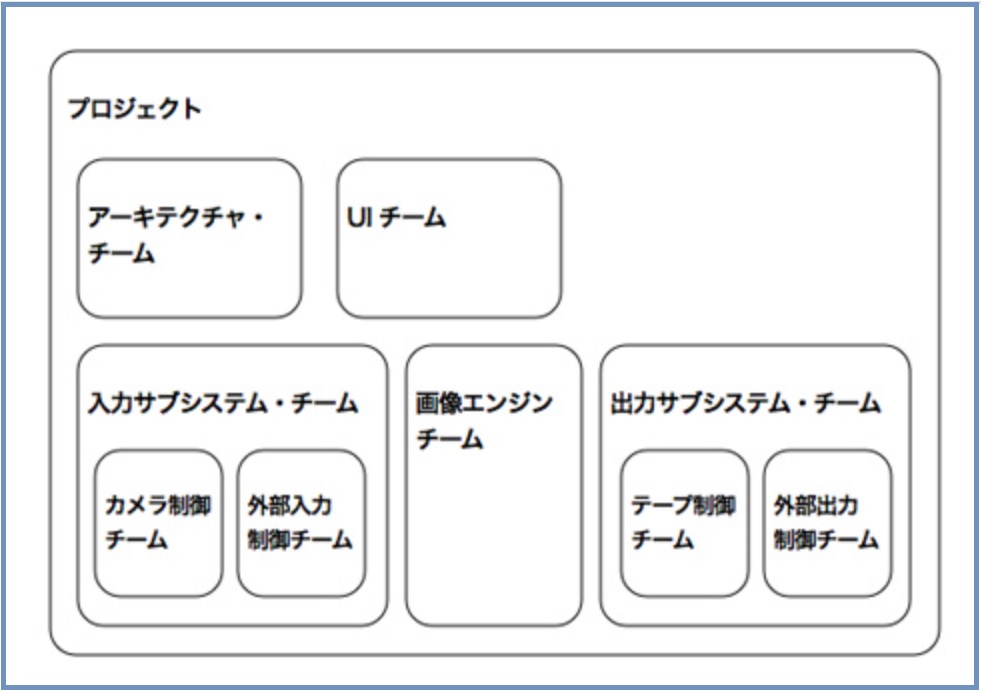
TOP

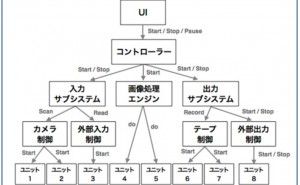
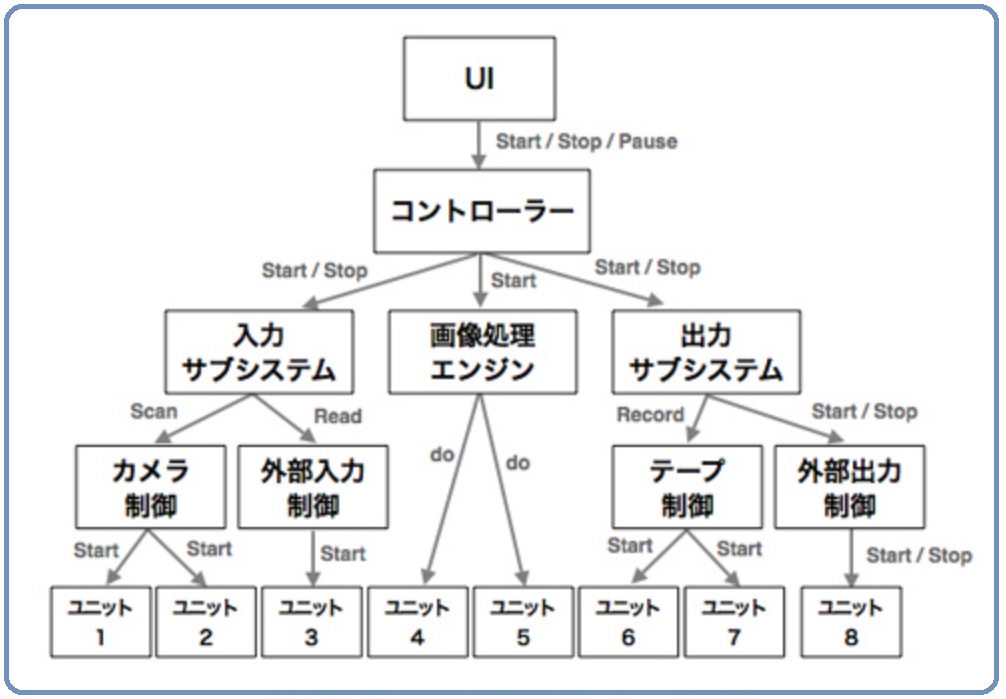
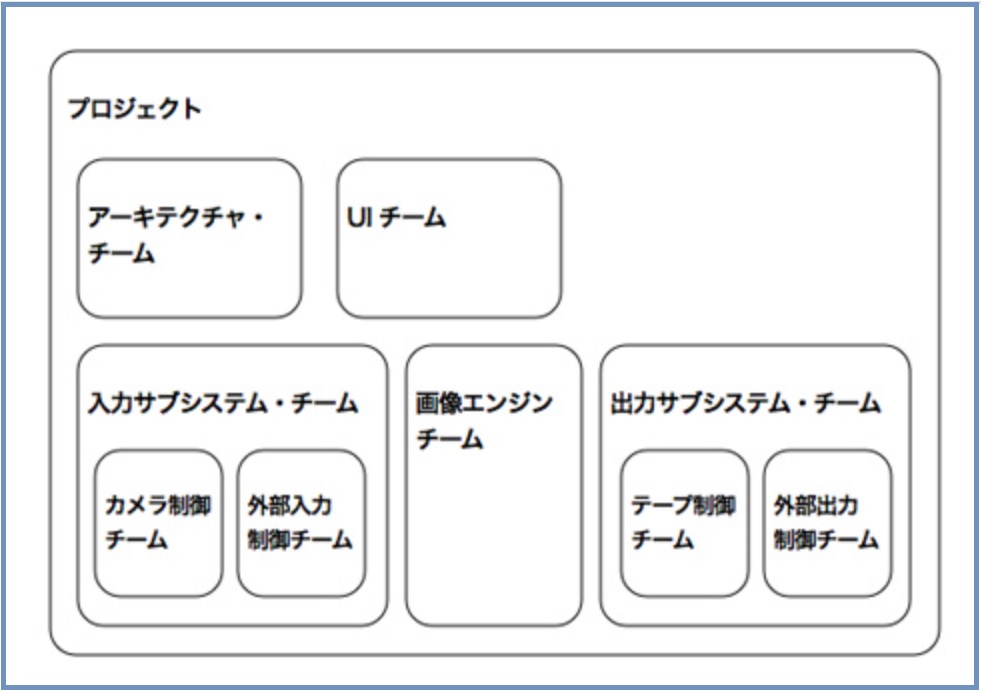
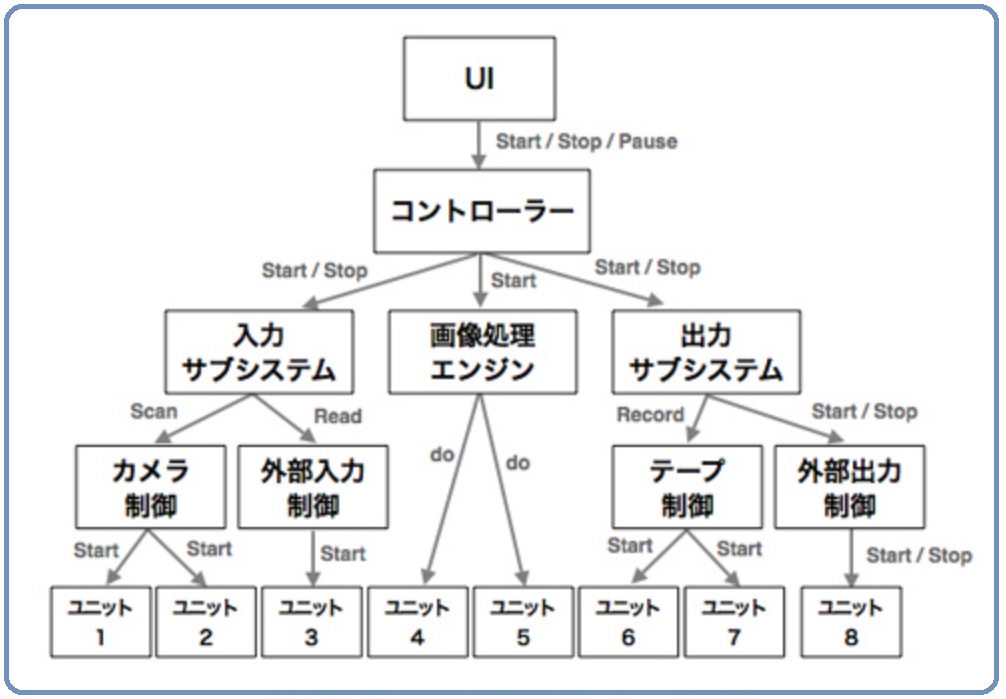
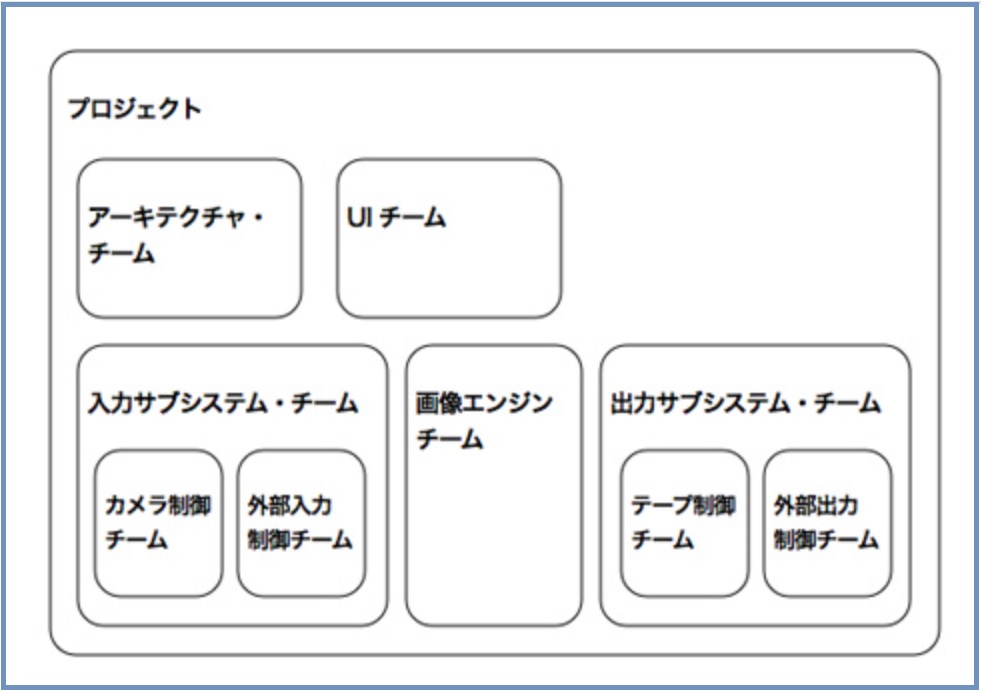
続きを読むには・・・
石橋 良造
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!
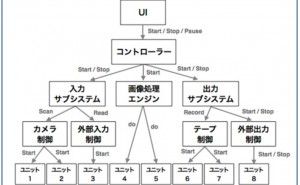
現在記事
前回はエドワード・デシの四段階理論で、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しました。今回も引き続き、本トピックについて解説しま...
前回はエドワード・デシの四段階理論で、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しました。今回も引き続き、本トピックについて解説しま...
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 「このテーマで良いんでしょうか?」と仰るのは技術者...
【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 「このテーマで良いんでしょうか?」と仰るのは技術者...
1.設計標準と最適なコストの例 前回のその2に続いて解説します。炭素鋼板という材料を用いて、機械に取り付けるカバーを設計するとします。形状は、L字...
1.設計標準と最適なコストの例 前回のその2に続いて解説します。炭素鋼板という材料を用いて、機械に取り付けるカバーを設計するとします。形状は、L字...
今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。 &...
今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。 &...
前回のその4:プロジェクトの進捗管理に続いて解説します。前回は CMMI を使い、要件管理、計画作成、進捗管理のポイントを紹介しました。多くの開発組織で...
前回のその4:プロジェクトの進捗管理に続いて解説します。前回は CMMI を使い、要件管理、計画作成、進捗管理のポイントを紹介しました。多くの開発組織で...
これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...
これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...
 2026/02/18(水)
2026/02/18(水)
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



