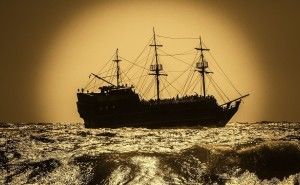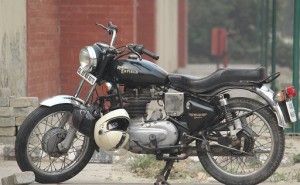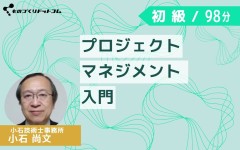『坂の上の雲』は司馬遼太郎が残した多くの作品の中で、最もビジネス関係者が愛読しているものの一つでしょう。これには企業がビジネスと言う戦場で勝利をおさめる為のヒントが豊富に隠されています。『坂の上の雲』に学ぶマネジメント、今回は、先人の知恵、定石と応用 (その3)です。
4. いくつもの課題を同時進行させる
プロジェクトの進め方では、いくつもの課題を同時進行させることが必要です。いくつもの課題を一つひとつバラバラに実行しただけでは、全部を同時進行させたときのような相乗効果は期待できません。全部の課題を同時進行させる、もっとうまいやり方をするという発想が必要です。
(1) 同時進行していた
日露戦争のシナリオでは、まず外交交渉として日英同盟締結がありました。元老の伊藤博文は、あの誇り高い大英帝国が日本のような弱小国と同盟などするもんか、とんでもないと思っていましたがこれは彼の思い込みでした。駐英公使の林董が、いやいやイギリスも南アフリカの植民地で起きていたボーア戦争に手を取られて、とてもじゃないが東アジアまで手が回らない。東アジアではロシアが勢力拡大をはかっており、イギリスにとって頭がいたい問題である。それを日本が阻止してくれると非常にありがたい、という状況を伊藤博文に説明しました。しかし、伊藤はこの話を信用しませんでした。明治維新前後における列強の強さを知っているから、ロシアと開戦するのはとんでもないことと思っていたからです。イギリスにとっては、日本を応援して日本とロシアが戦い、ロシアの東アジア進出の夢が砕けて日本もへとへとになって、もう帝国主義の列強には参加できないほどにお互いに疲弊するのが最もいいシナリオだったらしいのです。
このように、日露戦争にいたるシナリオが書かれていました。あらゆるところがぬかりなくできていたと言えるでしょう。列挙すれば、次のようなことが、『坂の上の雲』に詳しく書かれています。
・開戦前に国内経済界の重鎮渋沢栄一などに軍事資金の支援を要請する。
・開戦前にアメリカの世論を日本に好感を持つように金子堅太郎をアメリカに派遣する。
・開戦前に軍事資金を確保するために、高橋是清がイギリス、アメリカで外債の発行をする。
・明石元二郎がスパイを使ってロシアの後方攪乱をする。
・終戦後のポーツマス講和会議にはアメリカに調停を依頼する。
・日英同盟の前に海軍も陸軍も、明治維新の生き残りを一掃する人事を行なう。
・みんな大学校出身にしてパリパリの共通言語で話せる人間に揃える。
・軍艦の燃料となる石炭イギリスの無煙炭の買い付け。戦争中に使えるぐらいの量を仮押さえしておく。
開戦前に海軍大臣に決裁をあおぐ場面があります。それを海軍大臣の山本がサインする。その辺のところもすべて用意周到です。ところが、ロシアはすぐ勝てると思うおごりがあるから、あまり準備していないのです。日本は、このようにいろいろなことを同時進行させるシナリオがよく書けていたということです。そういうこともあって想定どおりに戦争を短期に終結させることができたのです。
(2) 全体構想を練ってから始める
プロジェクトの場合には、「やりやすいところから始めない」が鉄則です。何かを少し試しにやってみるのは良いことです。全体構想を練らないと本当に必要かどうかはわからないでしょう。実は余分な作業だった、時間やお金が無駄になったということがけっこうあるのです。はじめに全体構想を練るのが先決です。全体構想を練る手順もすでに確立されています。手順どおりにすすめることはよい方法です。ところが、手順どおりに進めることが徹底しているアメリカのプロジェクトマネジメントの標準
PMBOK:R*(ピンボック)には、全体構想のことは何にも書いてないのです。単に1つのプロジェクトをどう進めるか、ということしか書いてないのです。プロジェクトを実行する人と全体構想を練る人は、アメリカでは別なのです。
日本の標準ガイドブック
P2M: **には、スキームモデル(枠組み)をつくって、その後のサービスモデルまで用意されて、スキーム戦略で勝つようにしましょう、売りっぱなしではなくあとのサービスでも収益が出るようにしましょうとつくられています。日本人の弱いところをこう考えたらよいとちゃんと書いてあるのです。
【注】
PMBOK *(A guide to the Project Management Body of Knowledge、プロジェクトマネジメント基礎知識体系)
P2M **Project & Program Management for Enterprise Innovation、プロジェクト&プログラムマネジメント標準ガイドブック)
よく、やりやすいところから始めて、全体像をつかむことでいいのではないか、と質問を受けます。ところが、やりやすいところから始めると、どんどんそのまま進んでしまい、結局、全体像を考えなくなってしいます。ちょっと進むと、またすぐ次が見えてくる、またどんどん進む。結局、最後に全体を考える時間がなくなるのです。やりにくくても必ず最初に全体像をつかまないといけません。最初の時間がもったいないと思うし、始めるとそのうち全体像が見えてくるだろうと、ついつい...