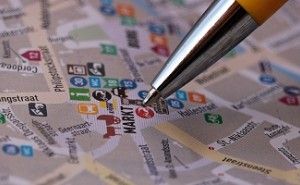【見える化 連載目次】
- 1. 情報の取り扱いで競争力をつける
- 2. 見えないことの方が大切なことがある
- 3. 職場の全員がコスト意識を持つには
- 4. 問題を顕在化してトップが改善の現場に参加
- 5. 管理板から活動管理板へ
- 6. 納期遵守率を向上させるには
- 7. 生産計画変更と現場
- 8. 生産現場の生産管理板
- 9. 変化の状況を客観的に見る
◆ 職場の5S ~ 変化の状況記録し気付きを得る
1. 毎日見ている職場の変化は見つけることが難しい
毎日見ているものほど見えなくなることは、普段の日常生活で誰でも経験があると思います。今朝の奥様はどんな服装でしたか?履いていたスリッパはどんな色?リビングのレイアウトで右から左の順番に何が配置されていますか?まったく思い出せませんね。ご自分のお子さんのこともあまり知らないというのは困りますが、私たちの記憶とはそんなものです。ましてや、毎日8時間以上も過ごしている職場も同じだと思います。
人間の脳は余りにも処理することが多いので、あまり問題のないことはすぐに忘れるようにして、新しい刺激を処理するようにできているようです。朝起きる時は身体を右にひねるか、それとも左にひねって起き上がるか?その時の手はどう置くか?など動作への判断処理は何万回もあるそうで、無意識で行われています。毎日繰り返しているようなことは、意識しなくても体が自然に動いているのです。改めて自律神経に感謝したいものです。
工場ではこのような判断処理がないように、通路の区分や置き場の表示標識、物に看板の取り付け、治工具置き場のシャドーボード、手順書や注意事項の貼り付け、呼び掛けにはポスターの掲示、台車やハンドリフターにもナンバープレートの取り付けなどを行い、作業者が見たらすぐに思い出せ、元の良い状態に戻すための仕掛けが整備されています。しかしいつの間にか、通路のテープやペンキがはがれてしまっている現状を毎日見ていると、段々と見えなくなり、区分を無視して歩いたり、台車を移動させたりしています。また取り付けていたものが壊れてしまっても、そのまま放置していたらそれが当たり前となってしまうこともしばしばです。
そのような状態は、エントロピー(無秩序の度合い)の法則でもご存じのように、自然と乱雑になっていくものです。また「以前はどうなっていたか」とか「どこにあったのか」という場合は、思い出し探すしかありません。でも記憶はあいまいになってしまっていますので、どこをどのようにしたか、すぐに思い出すことは非常に難しいものです。このためにも写真という便利なツールを使うことで、以前のことをはっきり思い出すことができます。
あるべき姿をいつでも確認ができるように、きちんと整備した時の状態を写真に撮り、それをラミネートで保護してその場所に貼り付けます。これはきちんと整備した時の状態を記録したものですが、ライン引きをしたり表示を行っても、はがれたり汚れたりすることが多く、一度乱れると規律は一気に低下してしまいます。そのためにも、あるべき姿の写真が目の前に貼ってあると、異常がすぐに分かり対応や処置が的確にできます。
2. 定期観察で変化の違いを発見
きちんと整備した時の状態表示だけでなく、定期的に工場内の様子を記録することで、色々な気付きが生まれます。工場内のレイアウト図を取り出して、色々な方向から工場の今の姿を記録していきます。最初は四隅から中央に向かい放射線状に撮影をしてみてください。そしてレイアウト図に丸印を付け、撮影した方向に矢印を付けておきます。気になった個所も含め、撮影をしてください。デジカメや携帯電話で気楽に撮って記録してみましょう。
大切なことは、撮影した個所の目印と方向をレイアウト図にきちんと記録することです。まず撮影と観察地点の写真を皆さんで鑑賞してみて、問題点がどの辺に多いのかレイアウト図に赤丸などを付けてみてください。撮影したはずの所が上手く撮影してなかったり、漏れがあったりするものですので、もう一度撮影し直すこともお勧めします。最初と二回目は随分と見る目が違い、必要な個所の撮影が自分自身で分かってきます。できれば複数の人と一緒に撮影をしてみてください。視点の違いも分かり、良い方の写真がどちらかも分かります。一回目は失敗するつもりで、最初から二回撮影するようにすれば、かなりレベルが上がっていき、狙い通りになっていきます。
写真を撮影することが目的ではありません。不具合点や変化点、または何カ月も変化していない個所も発見してください。あくまでも改善のネタにすることが目的ですので、できるだけ継続する仕組みを作ることが肝心です。
3. 改善の進化や経過も定期観察で
多くの工場で過去の改善前の記録がほとんどないようです。なぜないのかと尋ねますと「見せたくないものは、写真に撮っていない。いいところだけを意識していた」という返事が多くありました。またそういう記録をきちんと残す習慣がなかったこともありました。いいところだけを記録に残すことは誰でもやりますが、逆に見たくない、見せたくない場面も大切な記録として残すことが、改善のヒントになってきます。
今までどれだけ、どこをどのように改善してきたかについて、誰でも知ることができる貴重な資料になります。毎月記録に残すことで、改善の進捗やノウハウ集にもなってきます。2カ月や3カ月に一度となるとついつい忘れてしまい、元の木阿弥(もくあみ)になってしまった工場もいくつもありましたので、やはり毎月定期的に決まった日に観察していった方がよいでしょう。メン...