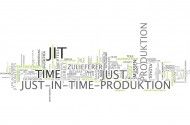【見える化 連載目次】
- 1. 情報の取り扱いで競争力をつける
- 2. 見えないことの方が大切なことがある
- 3. 職場の全員がコスト意識を持つには
- 4. 問題を顕在化してトップが改善の現場に参加
- 5. 管理板から活動管理板へ
- 6. 納期遵守率を向上させるには
- 7. 生産計画変更と現場
- 8. 生産現場の生産管理板
- 9. 変化の状況を客観的に見る
◆ 従業員に読まれる管理板の作り方教えます!
1. 今一度、管理板の目的を考える
コンサルタントが工場を訪問してまず見るものは、床やトイレなど普段気にしない個所です。実はそれだけではなく、色々なものを舐(な)めるように“看て”いきます。この「看る」は、看護の「看る」であり、手と目で触るようにしっかり事実を把握していきます。その中で工場の管理状態を集約して拝見できるツールの1つとして管理板があります。
ほとんどの工場における管理板の状態は、前月までの結果がグラフで示されている資料です。さらに目標値を示す線が表示されていないものも少なくありません。この管理板は一体何を目的に掲示され、関係者に何をしてほしいものかが、第三者として訪問した場合に、全く理解できないものと指摘させてもらいます。恐らくトップや管理者も当初は関心を持って見ていたかも知れませんが、その上司の皆さんも管理板を見て、一体どのようにアクションを取っていいものか、分からなくなってしまうものです。また管理板からはみ出ていたり、斜めにずれていたり、2枚、3枚と重ねられ見えなくなっているもの、古くなり色あせたものなど、まるで管理板は地獄八景のようです。
案内をしてくれる人たちにも色々と質問してみても、明快な返事は返ってきません。多くの場合は、機械的に毎月のデータを集計して資料を印刷して、義務的に貼り付けしているだけです。中には壁一面にA4サイズの綺麗(きれい)に印刷した資料を数十枚貼り付ける工場もあります。一枚一枚これは何を表し、異常か正常か、そして異常の場合は誰が、いつ、どのように、アクションを取り良否の評価するのですか?と尋ねても、口をモゴモゴとされてしまいます。これではせっかくこれらの資料を作成した人たちにも、余り意味のない作業をさせてしまい、彼らの作業意欲もなくなってしまいます。意味のある作業ならば仕事になりますが、これでは付加価値のない作業だけで終わってしまいます。
今一度この管理板の目的を考えてみますと、異常やバラツキを発見し、素早くアクションを取って、正常値に戻すことです。さらにその状態よりも、より良い状態に向上させるきっかけを作るものと考えます。従って、ただ掲示するだけでなく、この資料から何を訴えたいのか、そしてどうしてほしいのか、さらにどうなりたいのかなどを関係者に確実に伝えることです。その結果として、関係者が納得して常に改善していくという行動に変わっていくことを狙っているものです。
2. 管理板とルールはセットで活用
このような管理板を生きたものにするため、多くの工場で紹介しているのが、管理板にルールを一緒に掲示することです。
異常があれば、誰が、いつ、どのようなアクションを起こすかを、できるだけ具体的に記述します。異常があればすぐに対応しなければなりませんので、誰にでも分かる具体的行動が取れるような仕組みを作ります。完璧なものを最初から作ろうとされるから、いつまで経ってもできないことが多いのです。6割程度いいかなと思ったら、まず形にしてやりながら改善していけば良いと気楽に考え直すことです。失敗を恐れないという少しの勇気を持って、まず踏み出すことが大切です。
このルールは、常に変えていくものと考え方を改めます。いったん作成すると、憲法のように変えないものではありません。逆に一度決めて、もっと良い方法があれば即座に変えていくものと理解してください。著者の訪問しているところでは、3ヶ月を目途に更新するようにしています。人間の細胞もほとんどが3ヶ月で入れ替わるのと同じで「工場のルールや標準類もドンドン良いものに変えていきましょう」と背中を後押しています。工場も人間と一緒で生き物です。同じ細胞のままでは死を意味します。生き続けるためにも、常に変化できるように「まずは身近な管理板の管理からやっていきましょう」と声を掛けています。管理板に生の声も直接書き込んで行きましょう。
資料には緑色で目標線を書き、さらにアンドンラインとしてある異常値にその線を引きます。アンドンで異常を示しますので、その線の色は赤です。そのアンドンラインを超えた時に異常の内容も記入します。そして、誰がいつアクションを取るか、その結果も分かるようにレイアウトを工夫します。余り難しいことは考えずにまず作成して、やりながら独自のものを現場の人たちと一緒に作り上げて行けばよいでしょう。むしろこの帳票を使いなさいと指示をすれば、彼らはやらされ感を持ってしまい、結局は使わなくなってしまいます。管理板とルールの関係は、ご飯と味噌(みそ)汁、パンとバター、箸(はし)と茶碗のように、なくてはならない最強のコンビにしたいものです。
3. 毎日更新し、従業員の興味引く内容に
管理板は皆さんが毎日目をする場所に掲示してあるのが普通ですので、毎日の変化やバラツキを気付くものにしたいものです。朝礼の場所、シフト交代の場所などで、昨日の結果を説明して、今日から良い仕事や改善のヒントとして活用したいものです。
管理版には月間単位の指標を掲示するものが多くあります。これは確かに必要なものですが、もっと素早くアクションを取るためにも、日々の管理をグラフで表すことをお勧めします。市場変化の激しい現在では、前月の結果は死亡診断書も同然です。インターネットのブ...