1. ブルウィップ効果を取りあげる理由
(2) 販売見込みの「読み」を含めたフォーキャスト決定の運用・組織
(3) (1)(2)を除くその他のSCMの仕組み全体
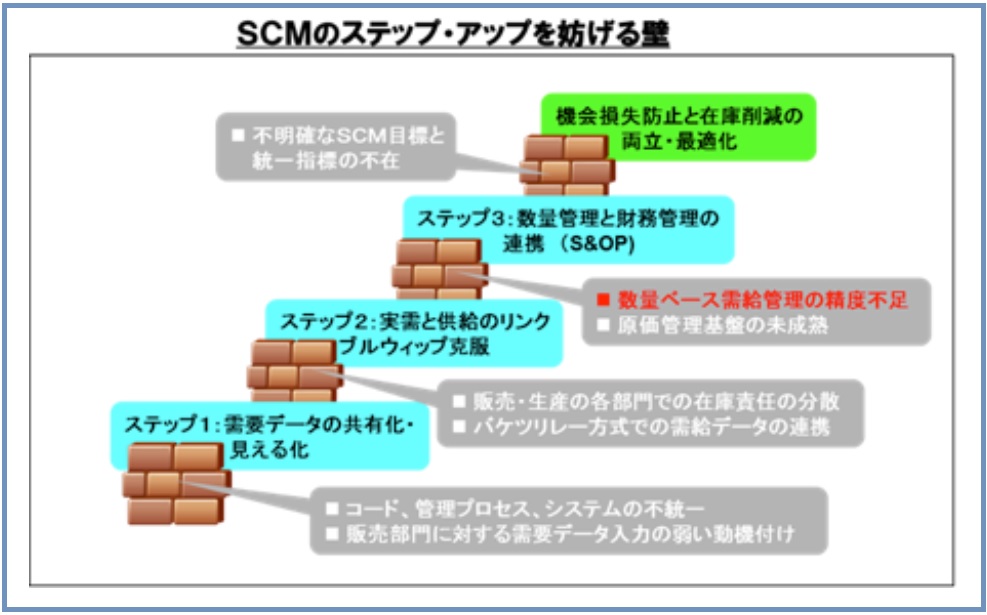
2. ブルウィップ効果とは
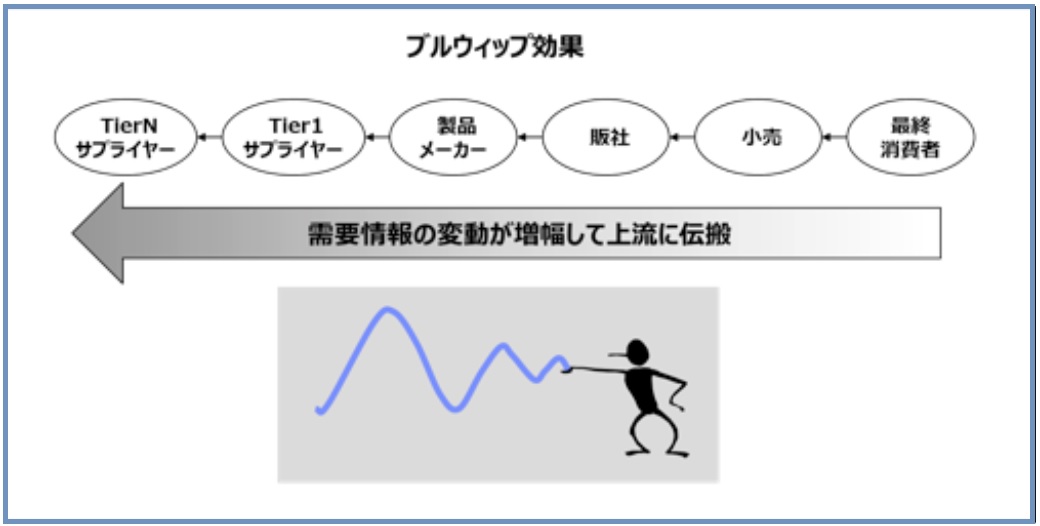
TOP

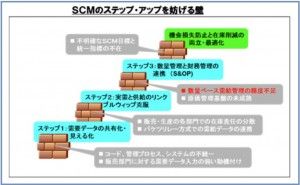
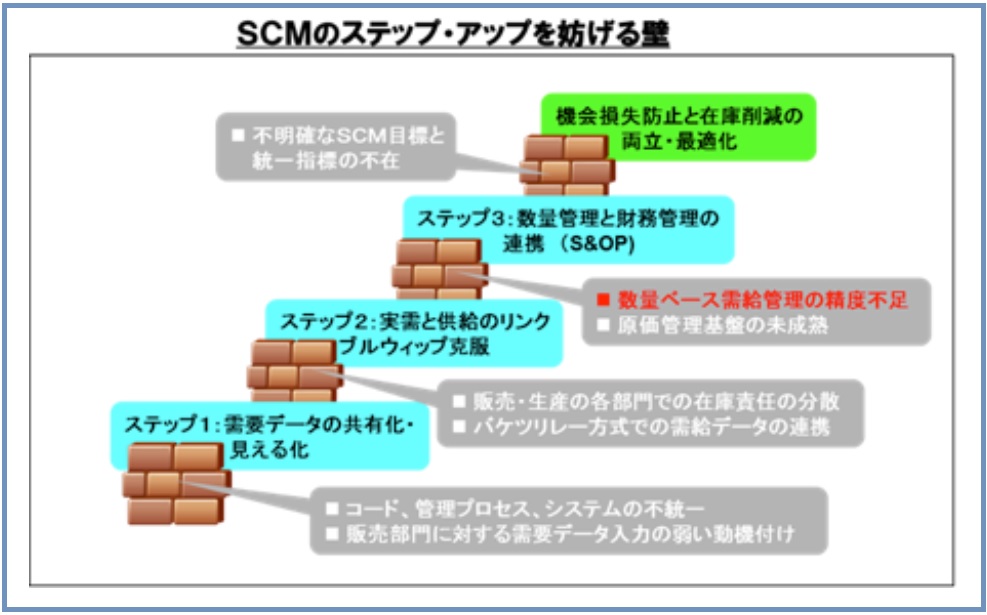
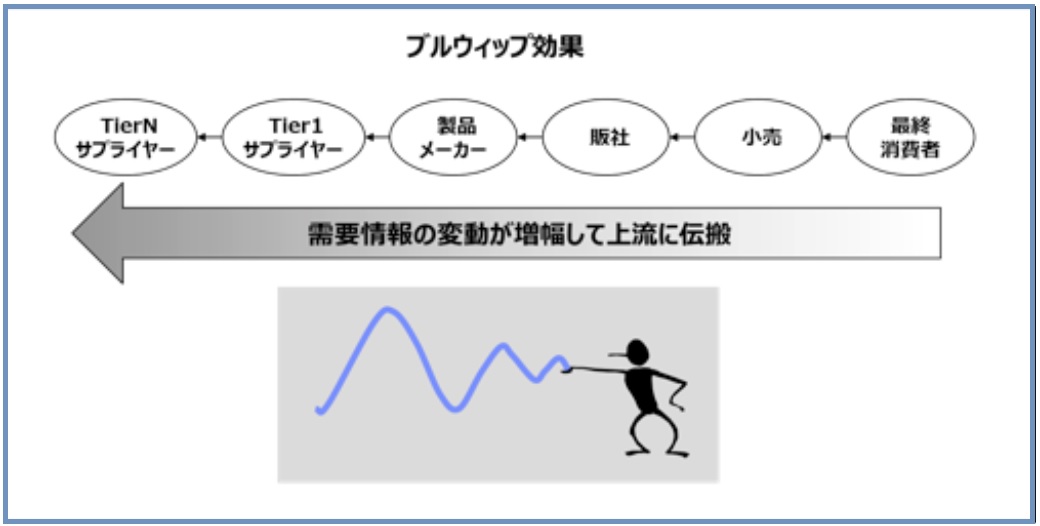
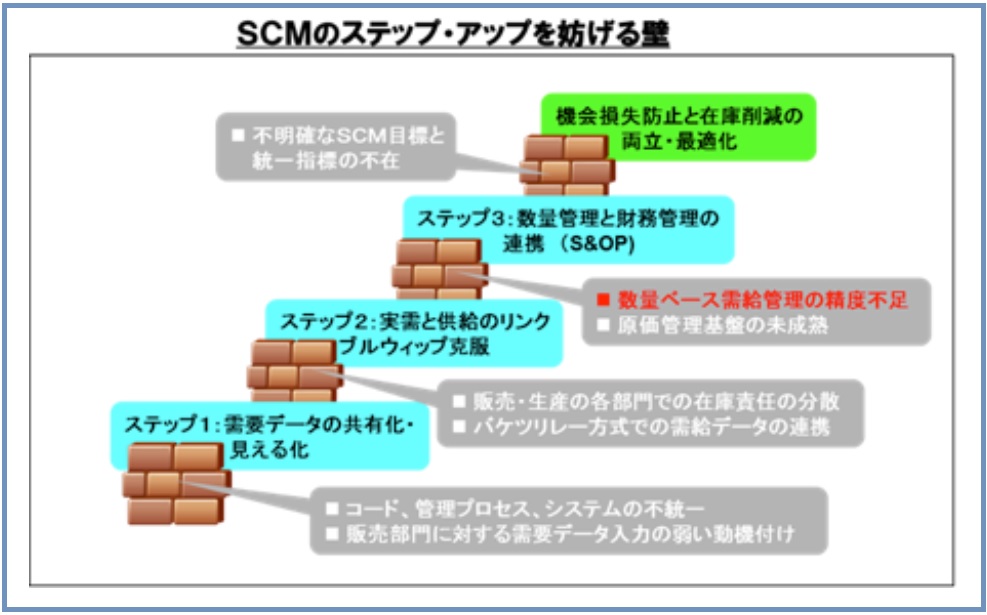
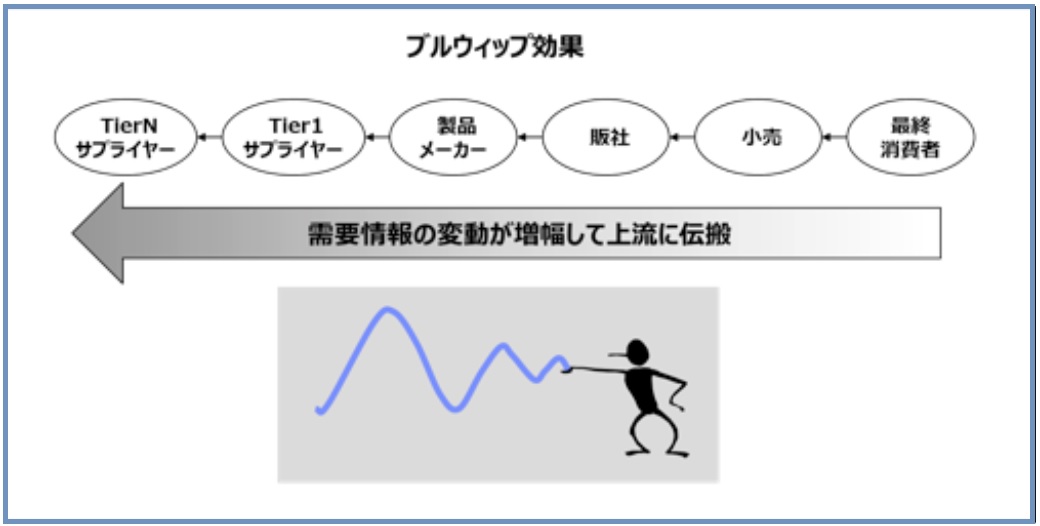
続きを読むには・・・
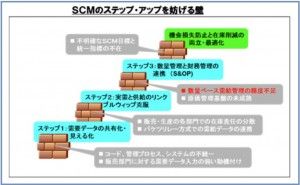
現在記事
儲ける輸送改善の記事が無料でお読みいただけます! ◆とってもおいしい輸送改善...
儲ける輸送改善の記事が無料でお読みいただけます! ◆とってもおいしい輸送改善...
1.サプライチェーンの同期化と能力 個々の業務スピードが高くても、そのスピード自体がバラバラだと在庫が溜まるため、機会損失が発生します。そういった機会...
1.サプライチェーンの同期化と能力 個々の業務スピードが高くても、そのスピード自体がバラバラだと在庫が溜まるため、機会損失が発生します。そういった機会...
第6回 道具4「物流会社選定ツール」(下) 前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 【選定ステップ6】回答...
第6回 道具4「物流会社選定ツール」(下) 前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『サプライチェーンマネジメントとは』 【選定ステップ6】回答...
◆ 物流エンジニアリングの取り組み ものづくりの場所を変更することは大変なように感じます。確かに大きな設備を移設して生産場所を変更することは大変で...
◆ 物流エンジニアリングの取り組み ものづくりの場所を変更することは大変なように感じます。確かに大きな設備を移設して生産場所を変更することは大変で...
1. 管理技術の伝授 皆さんの会社では、多くの物流業務を物流委託先に外注(アウトソース)しているのではないでしょうか。物流アウトソーシングを行って...
1. 管理技術の伝授 皆さんの会社では、多くの物流業務を物流委託先に外注(アウトソース)しているのではないでしょうか。物流アウトソーシングを行って...
◆ 観察力と分析力 荷主から値下げを要請されることはありますが、同時に物流効率化の要請を受けることもあります。荷主はサプライチェーントータルを効率...
◆ 観察力と分析力 荷主から値下げを要請されることはありますが、同時に物流効率化の要請を受けることもあります。荷主はサプライチェーントータルを効率...
コヒーレント・コンサルティング
SCMの効率を新しいKPIで見える化し、問題点を明らかにします。 新しいKPI 『面積原価』は、評価に時間軸を含めることで、リードタイム・在庫・原価のトレ...
開催日: 2026-10-06
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



