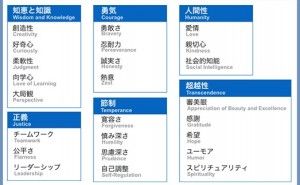▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
1. 得意・不得意の見極め
自分が何が得意か知ることは重要ですが、何を基準にしてそれを判断したらよいでしょうか。自己分析がしっかりできていればよいですが、そうでない時は本人の好き嫌いはあまり頼りになりません。自分の判断よりは周りの人の判断の方が信頼性は上がります。自分のことを客観的に見るのは難しいですが、人のことを客観的に見ることはそれほど難しくありません。人の判断と自分の判断がおおよそ合っている時は、自己評価も間違っていないでしょう。人の判断と自分の判断がずれている時は、自己評価が外れているかもしれません。
そして、最も信頼できることは結果に注目することです。結果に注目するときに、それまでの過程にも目が行きがちですが、あくまで最後の結果や成果に注目しま...