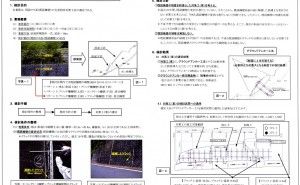▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
1. 共感と強要
相手の気持ちや立場を理解することは重要です。相手をよく理解したうえで考えや意見に賛同することを共感と言います。共感することによって多くの人が同じ考えや意見になったり、一つの考えに賛同します。共感において、周りの人は自主的に賛同します。様々な話を聞いた結果自分で決めます。これに対して、相手から強制的に賛同させられることを強要と言います。結果だけに注目すると、どちらも一人の意見や考えを周りの人が賛同する構図ができます。しかし強要の場合、自分の意志に関係なく相手の賛同させられます。嫌々、渋々でも賛同しています。
「共感する力がある」という人は話...