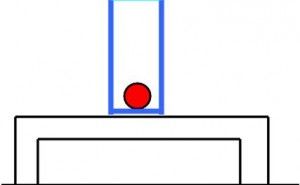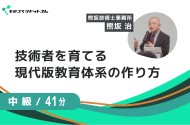「読み手のことを考えて技術文書を書くこと」に関する記事を何度か書きました。例えば、2018年2月14日に掲載した「読み手の立場に立って文書を書くとは」というテーマの記事です。今回は、「読み手のことを考えて技術文書を書くこと」についてこれまでとは違った切り口で解説します。
1.読書感想文の書き方
毎週土曜日の夜に放送されている民放の情報番組で、劇作家や脚本家などの三谷幸喜氏が今月2週にわたり読書感想文の書き方を説明していました。2週にわたる説明の中で特に参考になったのは、「どう思ったかではなく『どう変わったか』を書く」ということです。
多くの児童や生徒は、「読書感想文=本を読んでどのような感想を持ったか、つまり、どう思ったかを書かなければならない」と考えて読書感想文を書きます。しかし、このような考え方で読書感想文を書く必要はありません。このような決まりもありません。
「読書感想文≠どう思ったかを書かなければならない」と考えれば、「読書感想文=『どう変わったか』を書く」という考え方ができます。
2.読み手のことを考えて技術文書を書く
例えば、業務報告書(技術文書)を書くことを考えます。業務報告書を書く場合、「業務の成果をまとめる」あるいは「業務の成果を報告書にして記録する」という意識で書いている方が多いと思います。すなわち、これは、「業務報告書=まとめる、記録する」と考えて業務報告書を書くことです。
これに対して、「業務報告書≠まとめる、記録する」と考えれば、「業務報告書は、仕事の成果を伝えるために書く」という考え方ができます。すなわち、これは、「業務報告書=伝えること」と考えて業務報告書を書くことです。
「まとめる」や「記録する」という考え方で書くと、この考え方の中に「読み手」の存在が見えません。しかし、「伝える」という...