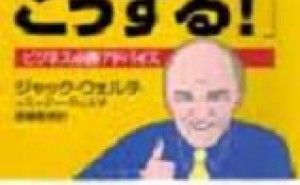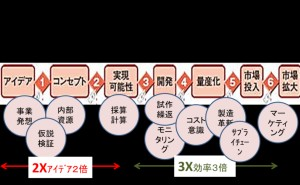1. メンターとは
筆者は、今まで技術士、キャリアカウンセラーあるいはメンターとして、主に研究者、技術者および工学部学生の相談にのってきました。それらの経験を踏まえ、今回は、良いメンターとどうめぐり逢うかについてまとめてみました。ちなみに、メンターとは、「仕事、キャリアあるいは人生に対して適切なアドバイスをしてくれる人」と定義されます。語源は、トロイ戦争に出てくる名教師の名前に由来しています。
メンターに期待することは、概ね次のようなケースと考えられます。
- 今後のキャリアパスの参考にしたい
- 仕事、キャリアあるいは人生で困ったときにアドバイスしてほしい
- 仕事や人生に対するスタンスや考え方のヒントを与えてほしい
2. メンターの現状と課題
従来のメンターは、職場の上司や先輩が一般的でした。最近、成果主義などの人事制度を導入する企業が増え、メールでのコミュニケーション代替化が進み、良い先輩や上司とじっくり話す機会が少なくなってきたようです。その対応として、いくつかの企業では、メンター制度を人事制度に組み入れています。役員自らメンターになったり、選抜された優秀な人材をメンターに指名したりしています。多くの社長には、コーチング手法を駆使できるコーチがついている時代でもあります。企業の求める成果には、ある程度近づいているかもしれませんが、真のメンターになり得ているでしょうか。
3. 筆者のメンターはどんな人か
参考として、筆者がめぐり逢ったメンターの何人かを少し具体的に紹介します。入社時には、一対一ではありませんが、機械加工実習では技能エキスパートの人であったり、設計実習では設計のエキスパートだったりしました。2年間メンターの役割を担っていただきました。しかし、企業から指名されたエキスパートの方々を真のメンターとは思っていませんでした。その責任者である技術部門長を、筆者自身が勝手にメンターに指名させていただき、実習ノートで本質的な意見交換をしていただきました。理由は、人材育成に対して想いが一番強い人だったからです。
製品の設計時には、設計部門の上司や先輩ではなく、電気関係を専門とする他部門のプロジェクトリーダーをメンターとしてお願いしていました。部門長としての業務やプロジェクトリーダーとして、多忙にも関わらず、物事に妥協せず、若輩からの議論にも嫌な素振りも見せず付き合っていただけたからです。例えば、書いた図面の線一本一本の意味を質問していただき、専門外の人から設計を教えていただいた感覚を、今でも鮮明に覚えております。真の目的は何かを常に問うていただける方だったのです。マーケティングや人生についてなど、他のテーマにも、場面、場面で多くのメンターがいました。
4. 良いメンターにめぐり合うには
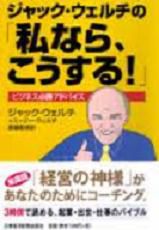 では、良いメンターにめぐり合うためにはどうすればよいのでしょうか。たまたま、ジャックウェルチの書籍である「私ならこうする(日経新聞社)」(...
では、良いメンターにめぐり合うためにはどうすればよいのでしょうか。たまたま、ジャックウェルチの書籍である「私ならこうする(日経新聞社)」(...