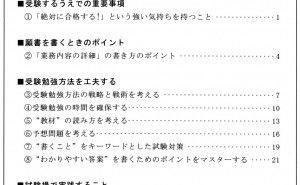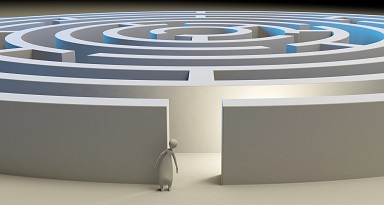
◆ メンタルモデルの違いに気付くことが、問題解決の第一歩
問題解決には問題分析も大切なのですが、その問題の構造を捉え「問題定義」を統一することが大切です。問題分析テクニックよりも「問題構造を見える化する」ことがポイントです。今回は、問題解決を停滞させる「 メンタルモデルの違い 」についてお話しします。
1. まずは問題のパターンを見つけ出す
私たちは、問題が発生するとその「問題現象や事象」を捉えます。事象や現象は、目に見えるコトや測定器などで測って認知ができる状態です。この「認知できる」状態を問題として捉えます。
また、この問題をよく観察するとパターンが必ず現れます。例えば
- 月末になると現象や事象が現れる
- ○時頃になると現象や事象が現れる
- 設備の点検後に現象や事象が現れる
などで、このパターンを見つけられないと、問題解決はここで停滞してしまいます。現象や事象をよく観察し、パターンを見つけ出すことが大切です。
そして、パターンが見つかると、それを発生させる原理原則が見えるようになります。この原理原則が起きないようにすれば、その問題は二度と発生しなくなります。
2. 次のステップは問題定義
ここまでは、観察や分析で原因の追及を進めることができます。しかし、これら観察や分析の前に必ず「特定」しておかなければならないコトがあります。それは、問題の定義です。
私たちは、問題現象や事象を捉えると、その人の経験や知識そして価値観によって、問題の捉え方が異なることが解っています。あなたの職場でも、なかなか問題解決が進まない時、その問題の捉え方がメンバーによって違っている可能性があります。
例えば、コップに半分の水が入っている場合
- Aさんは「水が半分も入っている。」
- Bさんは「水が半分しか入っていない。」
など、その現象や事象を違って捉えることがよくあります。
実は、この問題の捉え方が異なることで、問題解決がスムーズに進まないケースが多くあるのです。
3. 人それぞれ、メンタルモデルの違いがある
この問題の捉え方のことを「メンタルモデル」といいます。メンタルモデルの違いは人それぞれ、10人いたら10人違っていることも珍しくありません。まるでボタンの掛け違えの様な現象をチームの中に発生させ、問題解決がスムーズに進まなくなってし...