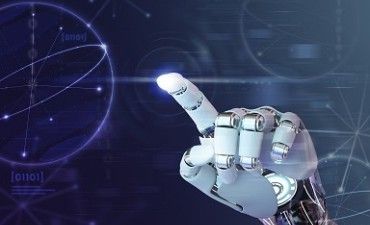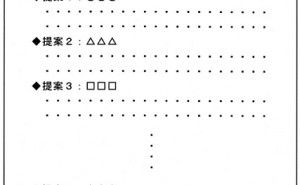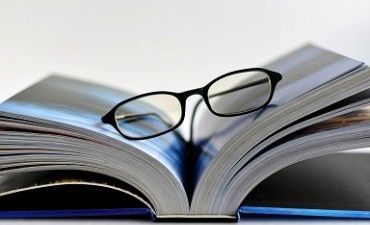▼さらに深く学ぶなら!
「ビジネススキル」に関するセミナーはこちら!
1. 過去の選択と責任感
大きな経験をすることによって人は成長すると言われます。いわゆる修羅場を経験した人です。修羅場ではなくても、人は必ずその時その時に選択をします。その選択の結果が現在の自分です。どの学校に行ったか、どの会社に入ったか、どの仕事を行ってきたか、などです。そして、そこまで大きな節目ではなくても、毎日小さな選択をしています。メールチェックを〇時までにすます、A、Bの順に作業しよう、顧客に△△を伝えるなど日々様々な行動にも選択が行われます。この選択をどれだけ自主的に行ってきたか、そしてその結果を主体的に受け止めてきたかが自分の経験となっていきます。
いわゆる修羅場はその選択の規模が大きいことや、選択せざるを得ない厳しい状況など肉体的にも精神的にも大きなプレッシャーがかかる場面です。そこに逃げずに正面から向き合ったからこそ大きく成長できたのです。この大きな選択と苦労を混同すると「苦労が人を成長させる」と思われがちです。苦労自身にはあまり意味はありません。苦労するくらい大きな選択が人を成長させます。
〇〇さんは責任感がある、または責任感がないと言いますが、責任感とは何でしょうか。「責任感がない」人は比較的分かりやすいです。時間、期限、締切を守らない。製品の品質を保証しない。相談しても対応が遅い、たらい回し。大事な約束を頻繁に忘れるなどがあります。一緒に仕事をすると非常に苦労するので、傷口を広げるとか、足を引っ張るなどと言われることもあります。ということは、この反対の人が責任感のある人となります。
責任感のある人、ない人の違いは何でしょうか。行動原理の中心にあるのが仕事の成果を達成することか、自分が楽をしたいか怠けたいか、ということが影響しています。時間を守ったり、良い製品をおさめるのは仕事の成果を達成するためです。そのために自分の時間と労力を使います。しかし、これらは自分が楽をするためには出来る限り避けたいことです。その結果、これに費やす時間や労力を削ります。当然得られた成果は小さく、モチベーションも低いです。
24時間全て100%である必要はありませんが、一度怠ける習慣が身についてしまうと、いざ100%の力を出そうとしても、出し方がわからなくなることです。これが最も厄介なことです。常に一定量以上に責任感をもって行動していれば、いざという時に100%の力を出すことができます。
2. 仕事と価値、仕事の対価
仕事では何か社会や人のために役立つことを行います。そして、その対価として金銭的な報酬を受け取ります。稼ぐことについては色々な意見があると思いますが、仕事の対価、報酬を受け取ることは自然なことです。報酬の金額はあなたが行った仕事の内容を顧客が認めた数値です。「その製品、サービスなら〇〇円の価値がある」と顧客が思ったから仕事が成立し、報酬を受け取るのです。
自分と顧客のお互いが仕事の内容と金額の認識が一致していればよいのですが、これがずれてくると対立が生まれます。「自分の仕事にはもっと大きな価値がある」「あなたの仕事の価値はそこまで大きくない」最終的に仕事の価値を決めるのは顧客になります。しかし、別の顧客、別の地域、別の分野では価値が変わることもあります。あなたの仕事に対する基準が変わるので、同じ内容でも顧客が認める価値は変わります。誰でも出来る簡単な仕事はどの社会でも求められていますが、その価値は高くありません。しかし仕事の特別性や専門性が高まるほど価値は上がりますが、それを認めてくれる顧客は限られてきます。
現状、自分の仕事の価値に不満がある時はその内容が一般的なものなのか、専門的すぎて理解されにくいのか見直してみるとよいかもしれません。
◆連載記事紹介:ものづくりドットコムの人気連載記事をまとめたページはこちら!
▼さらに深く学ぶなら!
「ビジネススキル」に関するセミナーはこちら!