【製品設計:ミス防止対策 連載目次】
② 具体設計に着手する
③ 技術的手段(方式)の妥当性を確認する
④ 実際に試作検証して設計通りのものか確認する
⑤ 最終のアウトプットとして、設計図面をリリースする
1.標準化の意味
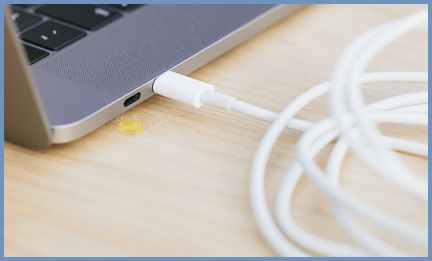 「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。
「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。TOP

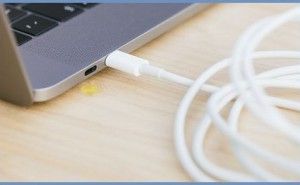
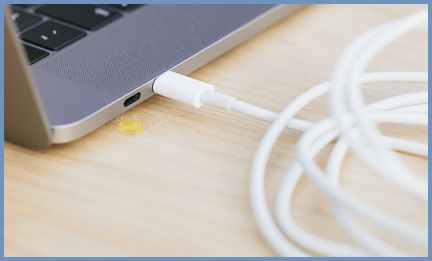 「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。
「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。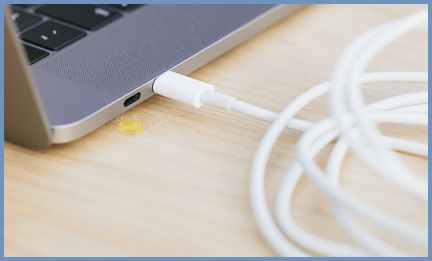 「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。
「標準化」という言葉はよく聞きますが、例えばUSB接続の機器はUSBの規格を満足するように作られています。USBはコンピュータと端末装置を接続するための規格として最も普及している標準インターフェース規格です。続きを読むには・・・
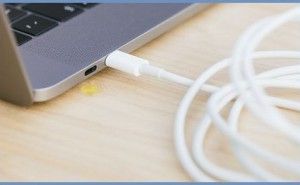
現在記事
1、返報性の原理 今回は返報性の原理についてです。返報性の原理とは、人間の持つ心理の一つです。 人は他人から何らかの施しを受けた場合に、お返し...
1、返報性の原理 今回は返報性の原理についてです。返報性の原理とは、人間の持つ心理の一つです。 人は他人から何らかの施しを受けた場合に、お返し...
今回は企画提案や初期開発でつまづきやすい、「開発商材の良さ」が相手に伝わらないという悩みの解...
今回は企画提案や初期開発でつまづきやすい、「開発商材の良さ」が相手に伝わらないという悩みの解...
1. 技術開発戦略立案の背景 いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は...
1. 技術開発戦略立案の背景 いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は...
1. RPA~パソコン作業を自動化 RPA(Robotic Process Automation)とは、様々なデータソースを参照しながら行う定型的...
1. RPA~パソコン作業を自動化 RPA(Robotic Process Automation)とは、様々なデータソースを参照しながら行う定型的...
前回は進捗管理の基本的な考え方を紹介しました。今回は、この考え方にしたがってどのような方法で実際に進捗を把握できるのかを紹介したいと思います。具体的な話...
前回は進捗管理の基本的な考え方を紹介しました。今回は、この考え方にしたがってどのような方法で実際に進捗を把握できるのかを紹介したいと思います。具体的な話...
※イメージ画像 1. 自社技術起点に新商品開発 今回は、精密鍛造金型メーカーとして創業し、現在は研究開発から部品製造まで精密鍛造に関するトータル...
※イメージ画像 1. 自社技術起点に新商品開発 今回は、精密鍛造金型メーカーとして創業し、現在は研究開発から部品製造まで精密鍛造に関するトータル...
合同会社高崎ものづくり技術研究所
製造業に従事して50年、新製品開発設計から製造技術、品質管理、海外生産まで、あらゆる業務に従事した経験を基に、現場目線で業務改革・経営改革・意識改革支援に...
開催日: 2026-03-18
開催日: 2026-03-26
開催日: 2026-02-17
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



