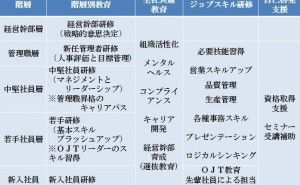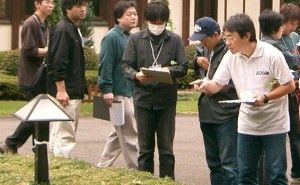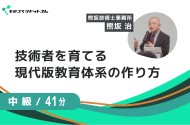【教育研修の進め方 連載目次】
人事評価制度を作ったものの、実際に評価を担当する管理職の意識や能力が不足している。そんな悩みを抱えている企業は多いと思います。そんな時、人事担当者が考えるのが、いわゆる人事評価者研修です。「人事評価制度を導入するなら、管理職に対して人事評価者研修をきちんと実施して欲しい」評価される側である一般社員からも要望があがってくるものです。
なぜ、そのような声が出るのでしょうか?それは一般社員から見ると、管理職が部下を評価する能力が不足していると思われているからにほかなりません。部下から見ると「甘い上司がいると思えば、厳しい上司もいる。どう見ても優秀とは思えない社員が高い評価を得ているのは納得できない!」そんな思いを抱いているのです。
というわけで人事担当者は人事評価者研修を企画します。一般的な人事評価者研修と言えば、ビデオを視聴して、あるいは特定のケースを読んで、評価の目線を合わせるのが普通です。ところが、こういう研修は何度やっても、実際にはほとんど役に立たず、現実の問題が解決することはありません。そればかりが、「評価基準の尺度や着眼点が現場の実態と合わない」とか、「評価することに時間がかかり過ぎて、肝心な仕事ができなくなる。」など、管理職の反発を招くことさえあります。
いったいなぜこんなことが起きるのでしょうか?それは、人事評価者研修の目的が部下の行動の評価基準の尺度を合わせるための研修になっているからです。つまり人事評価の本質が研修の目的となっていないというわけですから、失敗するのが当たり前なのです。
では、人事評価の本質とは何か、それは人事評価とは人材育成のためにあるということです。したがって、管理職が人事評価制度の運用を通して、部下を育てるという当たり前の心構えを醸成し、そのためにやるべきことを理解してもらうことが人事評価者研修の本質的な目的なのです。つまり、部下の能力を評価するというよりも、何が強みで何が弱みなのか、そのためにどういう指導をすべきかを把握することです。したがって、人事評価で大切なことは、評価時期に評価シートをどうつけるかではなく、管理職の日々の行動であり、部下をどう育てるかにあります。この当たり前のことを理解させ、実際に行動させることが重要であり、目線合わせの人事評価者研修など何の役にも立ちません。
人事評価者研修で重要なことは、まずはその本質的な目的を理解させることです。そして日々の管理職の行動が部下育成につながるという、当たり前の心構えを醸成します。そして、人事評価、つまり部下の評価結果は、自分の指導の結果に他ならないことを理解してもらうことです。子は親の鏡ということわざがあるように、部下は上司の鏡と同じなのです。また、部下の能力開発につながる人事評価をするためには、部下の仕事に関心を持ってよく観ることを徹底させるこ...