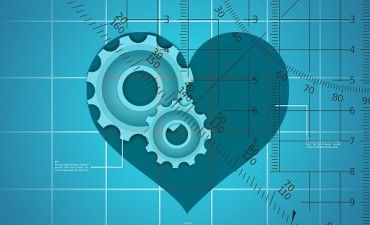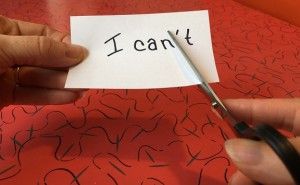▼さらに深く学ぶなら!
「行動科学」に関するセミナーはこちら!
▼さらに幅広く学ぶなら!
「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!
1. 目標設定時点で成功か失敗かは決まる?
失敗という言葉は「負けた時」や「上手くいかなかった時」に使います。その一方で、諦めた時、挑戦を止めた時が失敗という考えもあります。この考えでは目先の「損」は一つの結果にすぎないということです。どちらが良いというわけではありませんが、失敗にはこのような二つの考えがあります。後者の諦めた時が失敗という考え方も「最終的には成果が出る」ことがわかれば、目先の失敗は気になりません。諦めずに続けることができます。しかし「最終的に何の成果も得られない」と思うと、続けるのは難しいです。ただ大変な経験をして結局成果がないと時間と労力を無駄にするからです。
また、成果が出る...