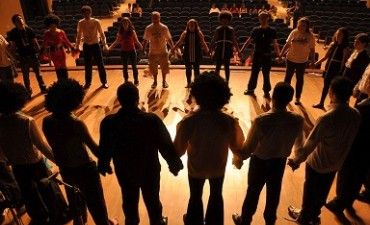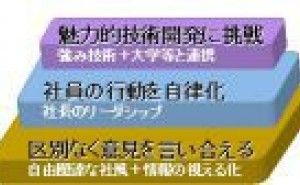春は「新入社員デビュー」の時期です。一日でも早く、会社や職場の雰囲気に慣れ、チームの一員として若い力を発揮してほしいものですが、それにはまず、リーダーが、新入社員の「協力と協調性」を育てていく必要があります。チームのパフォーマンスを高めるには、協力と協調が欠かせません。今回は、これらを高め絆を深くするための「ルーティーン」についてです。ひとり1人の意識を高め、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。
◆関連解説記事 社長と社員のコミュニケーション術【連載記事紹介】
◆関連解説記事 やろうと思っているけど できないことばかりの克服【連載記事紹介】
◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!
1.チームの信頼を高める『 同期行動 』
私は数年前、あるトレーナー資格を取得するため、集中トレーニングに参加をしたことがあります。これは10日に及ぶ集中型のトレーニングだったのですが、毎日セッションが変わる毎に、参加者全員でビートの効いた音楽でダンスを踊るというルーティーンの様なモノが繰り返されました。
「この年でダンスをしたことも無いオジサンが、音楽と仲間の動きに合わせながら踊るだなんて・・・」と思いながらも、周囲の雰囲気に流されながらダンスを「見よう見まね」でやっていたのですが、実は、心理学的にも「同じ動作行動( 同期行動 )」をするルーティーンは「チームの絆を深める」ということが解っていて、私も驚いた経験があります。
心理学の実験で、例えばラジオ体操のような「全員で同じ動作をする」行動をしたチームと、なにもしなかったチームの作業性を比較し作業性を観察すると、明らかに「全員で同じ動作」をしたチームのパフォーマンスが高まることがわかっています。
これは、【オキシトシン】という脳内ホルモンの分泌に関係があるといわれています。オキシトシンは、協力や協調性を高め「信頼」や「絆」を感じるホルモンです。
2.「 同期行動 」+「 笑顔 」で、さらに協調性と信頼を高める
「 同期行動 」は、オキシトシンがチーム内で作用し、作業に対する協力性や協調性を高め、パフォーマンスが上がるというわけです。
また、これらのチームでは「笑い」も増えることが解っています。一般的に人は、社会的地位が高くなればなるほど、人前で笑うこ...