【プラスチック製品の不具合事例 連載記事】
(3)プラスチック製品の不具合事例 (その2)
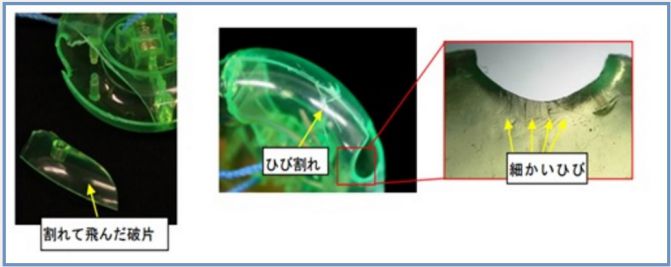
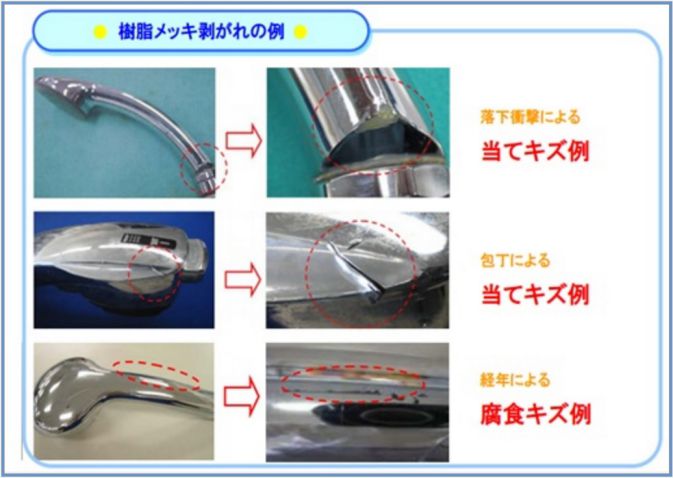

TOP

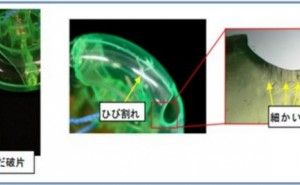
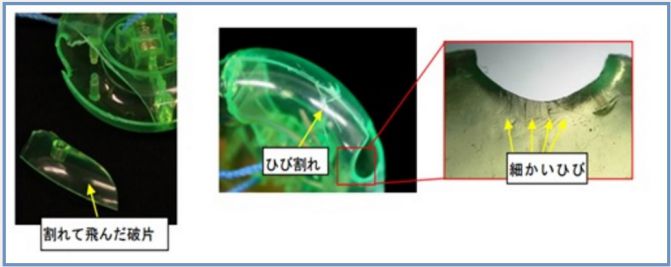
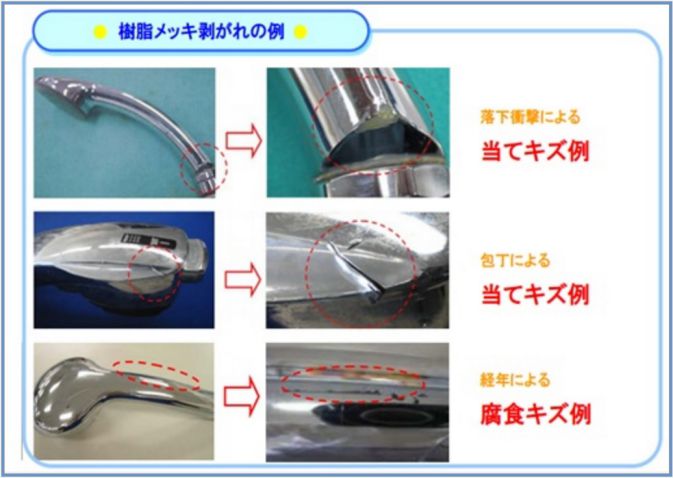

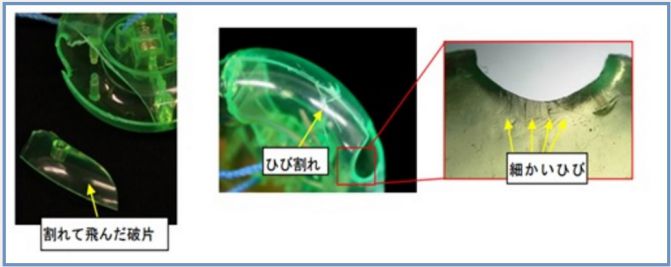
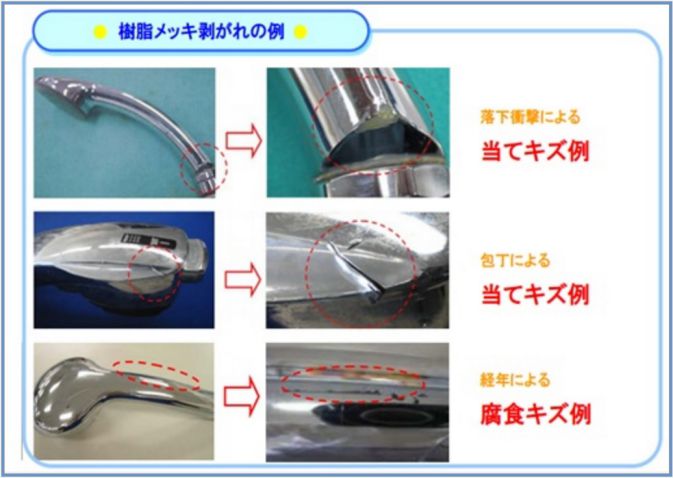

続きを読むには・・・

田口 宏之
田口技術士事務所
中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。
田口 宏之
中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。
中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。
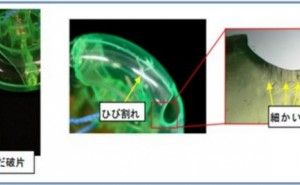
現在記事
広告を使用者に伝達する手段として色々なメディアがあります。新聞、テレビ、雑誌、交通広告、映画スクリーン広告、WEB広告、スマートフォンなど、私たちの日常...
広告を使用者に伝達する手段として色々なメディアがあります。新聞、テレビ、雑誌、交通広告、映画スクリーン広告、WEB広告、スマートフォンなど、私たちの日常...
1.表示の国際ルール 私たちは朝の起床から就寝するまで、必ず何らかの製品やサービスの恩恵を受けて生活しています。安全を楽しんで生活するために設けられ...
1.表示の国際ルール 私たちは朝の起床から就寝するまで、必ず何らかの製品やサービスの恩恵を受けて生活しています。安全を楽しんで生活するために設けられ...
【安全設計手法 連載目次】 1. フェールセーフ 2. フールプルーフ 3. プラスチックのクリープ特性1 4. プラスチック...
【安全設計手法 連載目次】 1. フェールセーフ 2. フールプルーフ 3. プラスチックのクリープ特性1 4. プラスチック...
建設・工事現場の落下物による事故防止についてですが、ISO 45001:2018(労働安全衛生マネジメントシステム)において「6.1.2.1 危険源...
建設・工事現場の落下物による事故防止についてですが、ISO 45001:2018(労働安全衛生マネジメントシステム)において「6.1.2.1 危険源...
♦ ビスから放電 ~ 静電気対策の基本はアース ちょっとの工夫で快適な作業空間に ある会社さんの作業台で静電気の電撃を感じました。おやっ...
♦ ビスから放電 ~ 静電気対策の基本はアース ちょっとの工夫で快適な作業空間に ある会社さんの作業台で静電気の電撃を感じました。おやっ...
◆ サイレントチェンジ多発の背景 2017年10月経産省・製品安全課から次のような文章が公開されました。「製造事業者は電気用品安全やRoHS規制等の...
◆ サイレントチェンジ多発の背景 2017年10月経産省・製品安全課から次のような文章が公開されました。「製造事業者は電気用品安全やRoHS規制等の...

田口 宏之
田口技術士事務所
中小製造業の製品設計の仕組み作りをお手伝いします!これからの時代、製品設計力強化が中小製造業の勝ち残る数少ない選択肢の一つです。
会社概要
-会社概要
© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ
ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!
Aperza IDでログイン
Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。
今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします



