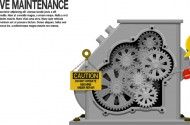在庫は罪庫と呼ばれる通り、在庫は持たない方がいいのですが、現実には物流倉庫でこれらの在庫品の管理をすることになります。物流倉庫内の在庫金額は棚卸をして把握する必要があります。各品目の単価と数量を調べて在庫総額を求め、これが期首在庫や期末在庫金額になります。ちなみに、期中在庫は一般的には(期首在庫+期末在庫)÷2で求められます。
物流倉庫の在庫ですが、実は「保管費」と呼ばれるコストが別にかかっています。これは以下のものがあげられます。
1.貯蔵保管に要する設備費用及び光熱費など(自社倉庫の建設費または倉庫の原価償却費なども含む)
2.保険料(倉庫への保険)
3.運搬費用(人件費)
4.棚卸し費用(人件費)
5.陳腐化、設計変更による未利用品、目減りや盗難、台帳との差異による損失処理
6.資本の費用(在庫はその分資金を投資することになり、この資金調達借入金利、及び在庫金額分を他の投資に回せない機会損失なども含む)
それぞれは、経理部門からデータを取り出すことができます。この保管費ですが、保管費率(Carrying Cost %)であらわされ、1年間の1個当たりの保管費が単価の何%かを意味します。
事例を挙げますと、日用雑多用度品の製造・販売会社A社の在庫(期末在庫)は、8,000万円で、保管費率は25%でした。
例えば製品aの単価が1000円であった場合、保管費率25%ですから年間に1個当たり250円の保管費となります。または、「期末在庫8,000万円の在庫ボリュームだが、年間にこの金額の25%にあたる2,000万円のコストが別にかかっている」と捉えると保管費率の実感が湧きます。
この保管費率を考慮すれば、一度の大量購買による割引単価も、実は必ずしも企業のメリットにならず、むしろ割引は少なく、小ロットでの仕入がメリットのある場合もあります。このA社は、人件費以外で陳腐化・未利用品の帳消し処理、それと同時に企業規模からみても過剰在庫からくる資本費用・機会損失のウェイトが大きい状況でした。
当たり前ですが、最低限の人員で倉...
 在庫は罪庫と呼ばれる通り、在庫は持たない方がいいのですが、現実には物流倉庫でこれらの在庫品の管理をすることになります。物流倉庫内の在庫金額は棚卸をして把握する必要があります。各品目の単価と数量を調べて在庫総額を求め、これが期首在庫や期末在庫金額になります。ちなみに、期中在庫は一般的には(期首在庫+期末在庫)÷2で求められます。
在庫は罪庫と呼ばれる通り、在庫は持たない方がいいのですが、現実には物流倉庫でこれらの在庫品の管理をすることになります。物流倉庫内の在庫金額は棚卸をして把握する必要があります。各品目の単価と数量を調べて在庫総額を求め、これが期首在庫や期末在庫金額になります。ちなみに、期中在庫は一般的には(期首在庫+期末在庫)÷2で求められます。