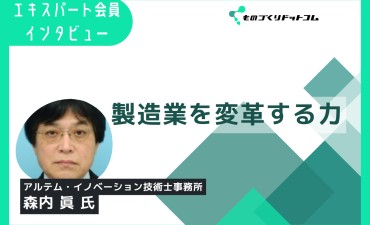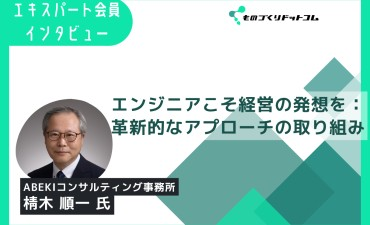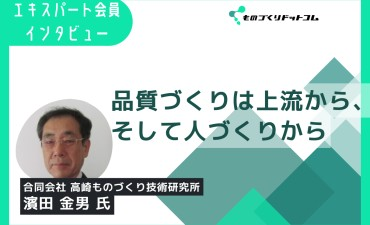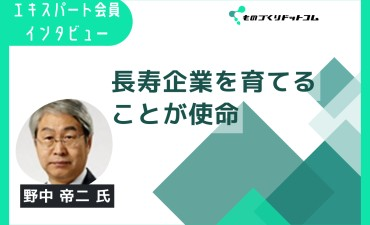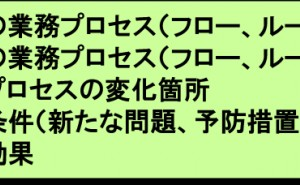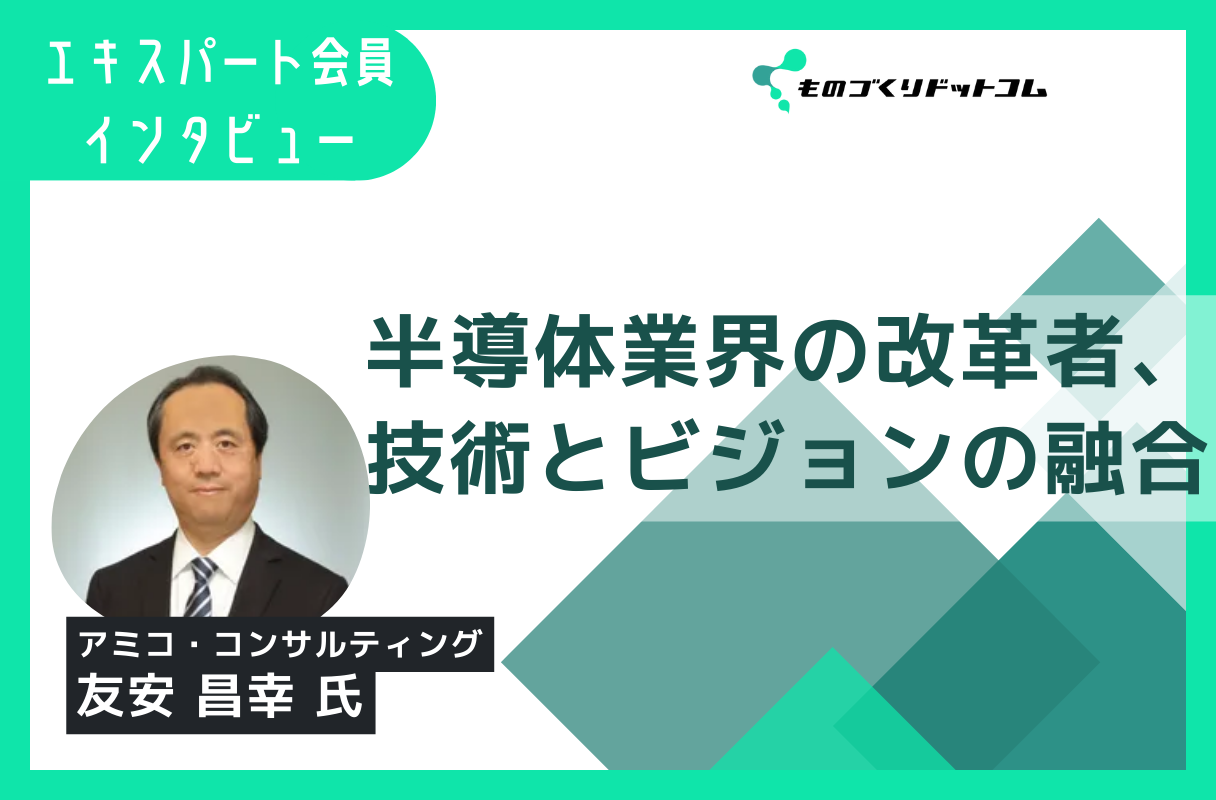
●はじめに●
半導体業界は、革新的な技術とその応用が社会の発展を加速している分野です。この分野で輝かしいキャリアを築き上げた友安昌幸氏は、東京エレクトロン株式会社での長年の経験を基に、今日の半導体技術の可能性とその将来について独自の洞察を提供しています。
エキスパート会員プロフィール
氏名: 友安 昌幸 (トモヤス マサユキ)
所属: 合同会社アミコ・コンサルティング
経歴: 東京エレクトロン株式会社、Samsung Electronics、華為技術日本株式会社にて要職を歴任
現職: 技術系コンサルタント、KPMG Japan アドバイザー
インタビュー
編集部: 友安さん、今日はお時間をいただきありがとうございます。
まず、長年のご経験について教えてください。
友安 昌幸: はい、喜んで。私は半導体産業において37年間活動してきました。東京エレクトロン、Samsung Electronics、華為技術日本などで、装置開発から事業開拓まで幅広く経験を積んできました。特に新しい技術の開発や問題解決には、強い情熱を持って取り組んできました。
編集部: 半導体業界の変化を間近で見てきたということですね。特に印象深い変化はありますか?
友安: 他の業界に比べて、この業界は絶えず変化しています。半導体デバイスの構造の変化に伴い、用いられる製造装置が変わり、勢力図が書き換えられるということが何度かありました。それに即して言うと、オープンイノベーションの推進は不可欠です。プリコンペティティブ領域で、異なる企業や組織が協力し合い、新たな技術や解決策を生み出すことが、今日の産業には不可欠です。
編集部: なるほど。では、ご自身の役割について教えてください。
友安: 私の役割は、技術革新を通じて産業成長を支援することです。異なる視点から問題を見つめ、根本的な解決策を提案することに尽力しています。技術開発では、実用性と実行可能性を重視し、理論だけでなく実際に現場で機能する解決策を提供することを心がけています。また、新しい技術や手法の導入には、現実に即したアプローチが不可欠だと考えています。
編集部: そうしたご経験を通じて、半導体業界に対する見解はどのように変化しましたか?
友安: アプローチ、手法は特に変わるものではありません。他方、技術面ではいわゆるムーアの法則(実際はデナードの法則)が終焉し、単なるスケーリングから、構造、材料へと多様な変化が求められています。その変化を的確にとらえ、ビジネス機会、リスクを判断することが求められます。
編集部: 今後の半導体業界に対する期待やメッセージをお願いします。
友安: 半導体産業はこれからも大きな可能性を秘めています。この業界は、技術革新とともに成長し続けることができます。変化を恐れず、新しい挑戦を続けることが重要です。私はこれからも、自らの経験を活かし、業界のさらなる発展に貢献していきたいと考えています。革新的な思考と、異なる分野や企業間の協力が、未来を形作る鍵だと信じています。
インタビューを終えて
半導体業界での豊富な経験をお持ちの友安昌幸氏の言葉は、彼の深い専門知識と、業界への献身を明確に示しています。彼のビジョンと経験は、半導体業界において新たな道を切り開く力となると考えます。
友安氏に対する業務のご依頼は、彼の豊富な経験と知識を活用する絶好の機会です。
アドバイス・コンサルティング・講演依頼などのお問い合わせはコチラから(コーディネーターに連絡する)
友安昌幸氏のセミナー(2023年12月18日時点)



![[エキスパート会員インタビュー記事]現実的な改善を通じたものづくり支援の実践(福富 昇 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2240/897ffd93-6047-47bb-9a0e-335d61aba4d2-thumb.png?d=0x0)
![[エキスパート会員インタビュー記事] 品質工学の魅力とその創造性への影響(細川 哲夫 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2258/212d98d5-c04e-4b10-9e31-1b91590aa34a-thumb.png?d=0x0)
![[エキスパート会員インタビュー記事]食品業界の改善活動から始まった多面的な改善アプローチ(小松 加奈 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2264/a9eb64e5-28e8-47eb-a839-d2547966154e-thumb.png?d=0x0)
![[エキスパート会員インタビュー記事]製造業の未来を切り拓く: 小山太一の生産性改革への道(小山 太一 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2263/04b0f07d-717c-4166-bfb4-558847753c7c-thumb.png?d=0x0)