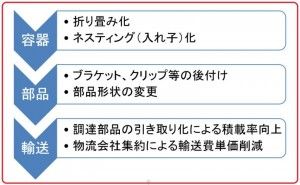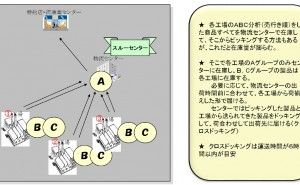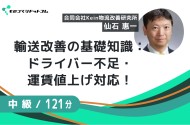◆井の中の蛙の物流業
自分たちが市場の中でどのような立ち位置にいるのか。ライバル会社に比べて物流現場の水準が勝っているのか、負けているのか。そのギャップはどれほどまであるのか。いろいろな会社の人たちと話をしていると自社のポジションについて明確に認識していないことに気づきます。自社のこういった点について結構無頓着なのです。この世の中競争社会ですから、自分たちの立ち位置がわかっていないと今後どのような方向に進んでいったらよいのかがわからないのです。
たとえば物流倉庫で仕事をしている人たちに聞くと、他社はおろか、自社の別の倉庫さえも見たことが無いという声が返ってきます。これではまったくの“井の中の蛙”状態です。外が見えていませんから、自分たちで好きなペースで仕事をしているのです。この状態は居心地は良いかもしれません。どこかと競って勝たねば、といったプレッシャーが無いからです。しかし一番怖い状況でもあるのです。他社はもっともっと先を行っている可能性が大きいからです。
日本は島国です。江戸時代には鎖国制度を保っていました。その結果、欧米各国に比べて産業の発展が大きく出遅れました。物流業務でもまったく同様と考えた方がよいでしょう。なぜならばマイペースで進めてきた結果、5年後には他社と比べ物にならないほどの差がついて、結果的に会社が倒産してしまった、ということになりかねないからです。
営業であれば売上高や利益に敏感です。常に「数字」に追われている状態です。一方で物流はどうでしょうか。今の自分たちの状態を数字で示せるでしょうか。この「数字」という点でも物流は他の産業に大きな後れを取っています。物流に携わる人の中には数字が苦手という人がたくさんいます。
数字で状態を示せなければ、今が良いのか悪いのか、まったくわからないということと等しいのです。レーダーなしに飛んでいる飛行機のようなものです。では具体的にこの状況をどのように打破していったらよいのでしょうか。
◆他業界を見ると物流現場が変わり、作業生産性も大幅に向上
最低限、月々の結果系指標で自分たちのパフォーマンスを把握しなければなりません。たとえば物流業務での売上高と利益です。よく聞く話としては、物流サービスを提供しているものの、その得意先向け業務がどれくらい儲かっているのかわかっていない、ということが挙げられます。
同じような商品を複数の得意先に届けていることを想定して考えてみましょう。得意先X社には毎週1回ケース単位で届けます。一方で得意先Y社には同じ商品を毎日ピース単位で届けるとしましょう。当然のことながら後者の方が物流サービス水準は高いと言えます。しかしサービス水準が高いということは原則としてコストも多くかかります。この例でよくあるパターンがX社、Y社向けともに「同じ価格」設定となっていることです。これは非常に不思議な現象ですが本当によくある話です。
もしかしたら営業マンが仕事を取りたいがために格好をつけただけなのかもしれません。あるいは正しい価格設定のノウハウが無かったのかもしれません。しかしこのようなことをやっていたら会社が儲かるはずがありません。営業は単に仕事を取ってくるというより、「儲かる仕事」を取ってくることが仕事であることを肝に銘じなければなりません。
では次にコスト系に目を向けてみましょう。倉庫内での作業のやり方で物流コストは大きく違ってきます。これもよく見かける光景です。それはピッキング工程で発生するさまざまなムダです。その一つが「通路幅」です。流通業での物流でよく耳にする不思議な理論。それはピッキング場の通路幅は「台車が2台すれ違える」幅だということ。幅が1m...