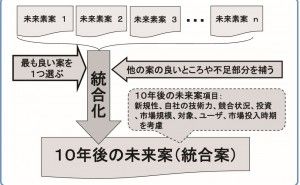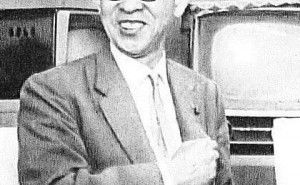1.荷物を振り分けて乗せるラクダを見て砂漠用の鉄道軌道を考案した、フランスの鉄道技師ラルティーニュ
フランス植民地時代のアルジェリアの鉄道技師ラルティーニュは、鉄道が砂漠には不向きだと考えていました。砂嵐が来ると線路が砂に埋まって、運行が不可能になる事態がしょっちゅう起こるからです。これを何とかしないと、せっかく鉄道を建設しても無駄になってしまいます。
そこでラルティーニュが考案したのが、地上数メートルの高さに軌道をつくり、それにまたがるようにして2つの箱型車両を走らせるというものです。彼は振り分けにした荷物を背に乗せているラクダを見て、この砂漠用軌道を思いついたそうです。
 2.海辺の砂にコールタールがしみ込んでいくのを見てダイナマイトを発想した、スウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベル
2.海辺の砂にコールタールがしみ込んでいくのを見てダイナマイトを発想した、スウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベル
濃い硫酸と硝酸をグリセリンに混ぜたニトログリセリンは、非常に危険な爆発物であるために、震動に弱く運搬することができませんでした。この危険ではあるが威力のあるニトログリセリンを、トンネルや鉱山を掘ったりするときに使えたら非常に便利だと考えていたスウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベルは、ある日海辺で船にコールタールの缶を積むようすを見ていたところ、缶に穴があいていて、コールタールがもれて砂浜にしみ込んでいきました。
それがヒントとなってノーベルは、研究の結果、海底や湖の底にできる硅藻土にニトログリセリンをしみ込ませると、震動が起きても爆発しないことを発見しました。これがダイナマイトの発明に、そしてノーベル賞の誕生につながってゆくのです。
3.床に転がっている紡ぎ車を見て複式紡績機を考案した、イギリスの大工 ジェイムズ・ハーグリーブス
1760年代当時の糸を紡ぐ作業は、紡ぎ車を手で回しながら一個の紡錘に糸を巻き取っていく方式でした。これを、一つの紡ぎ車で複数の紡錘を扱えるように考案したのがハーグリーブスです。この発明のヒントは、たまたまひっくり返してしまった紡ぎ車の動きにあったといいます。彼は、車を回すと8個の紡錘も同時に回る仕組みを考え、妻の名をとっ...