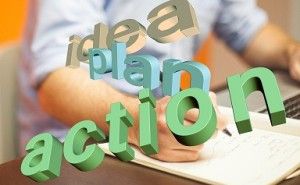自然界の現象を見て科学法則を思いつく事例はたくさんあります。そのなかのいくつかを紹介していきましょう。
1.ヘビがとぐろを巻く夢からベンゼンの構造式を発見したドイツの化学者、フレデリック・ケクレ
ドイツの化学者F・A・ケクレは、化学的にきわめて安定した性質を持つ炭化水素ベンゼンの構造式を探っていました。いくら考えてもなかなか解決できなかったのです。
しかし、1865年のある晩に見た夢が、その答えをもたらしました。その夢とは、原子の群が長い列になってヘビのようにクネクネと動きはじめ、やがて、そのヘビが自分の尾を食わえてクルクル回り出した、というものです。
この夢をヒントとしてケクレは、6個ずつの炭素と水素が環状につながっているベンゼン核の構造式を発見したのでした。
2.ハエが飛んでいる姿を見て、座標軸の理論を発見したフランスの哲学者、ルネ・デカルト
デカルトが、ベッドでうとうとしていると、ハエが飛んできて頭上を旋回していました。追い払うとハエは天井の壁に停まりました。
彼の位置からは、ハエは天井と壁がつくるちょうど三角の位置を飛んだりとまったりしているのが見えました。右の壁に行ったかと思うと、今度は左の壁、下がったかと思ったら天井にとまります。ハエは自由でいいな、とぼんやりと考えていましたが、なんとかハエの動きを正確に測る方法はないだろうかと考えはじめた時に、ハッと思いついたのでした。
それが空間における点の位置を決めるX軸、Y軸、Z軸の発見です。この「デカルト座標」は数学上の平面や第三次元の移動理論に、後世多大な影響を与えることになりました。
3.リンゴが木から落ちるのを見て、万有引力の法則を発見したイギリスの物理学者、アイザック・ニュートン
イギリスの物理学者で数学者のニュートンが、リンゴが木から落ちるのを見て、万有引力の法則を発見したことは有名な話で...