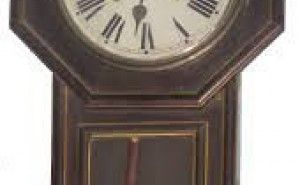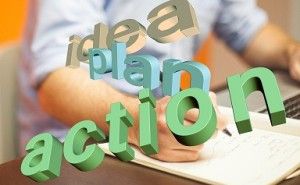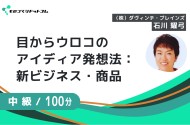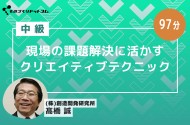1.ガルバーニの研究を受け継いで、最初の電池を考案したイタリアの物理学者アレッサンドロ・ボルタ
最初に電池を考案したのは、イタリアのアレッサンドロ・ボルタという物理学者で、1800年のことです。これは18世紀最大の発明ともいわれ、以後電気の利用が進むと同時に物理学や化学の分野にも大きな影響を与えました。ちなみに電圧の単位ボルトは、ボルタの名からとられました。
しかし、ボルタは先駆者の研究から大きなヒントを得ています。きっかけとなったのは、ボルタと同じイタリアの解剖学者ルイジ・ガルバーニ教授のある実験でした。当時、ガルバーニはカエルの筋肉を調べる実験を繰り返していましたが、カエルの足の神経にメスを当てたときに、たまたま摩擦電気を蓄える起電機を動かし、火花が飛んだところ、カエルの足の筋肉が激しくけいれんを起こしたのです。そこで、ガルバーニは、起電機に直接ふれないのにけいれんが起こるのは、カエルに「動物電気」があるからだと考えました。
ボルタはこの実験に大変興味をひかれました。最初はガルバーニの意見に同調していたのですが、自分でも実験を繰り返すうちに、動物電気は存在せず、二種の違った金属が接触すると電気が生じるという考えが導き出されたのです。そして研究をさらに進めて、ボルタ電堆【でんたい】をつくり、定常電流を得ることに成功し、これが最初の電池となったのでした。
 2.ランプの揺れを見て、振り子の等時性理論を発見したイタリアの物理学者ガリレオ・ガリレイ
2.ランプの揺れを見て、振り子の等時性理論を発見したイタリアの物理学者ガリレオ・ガリレイ
物理学者で天文学者のガリレオが、イタリアのピサ大学医学部の2年生の時でした。晩春の夕方、ピサの寺院に行ったガリレオは、寺男が天井からぶら下がるランプに火をつけるところを見ていました。天井から長くぶら下がるランプが大きく、静かに左右に揺れています。
じっと見ていた彼は、ランプの揺れる幅は段々小さくなっているものの、一往復する時間は同じよ...