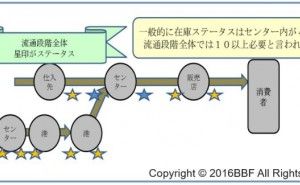トラック稼働率 保有能力を目いっぱい使おう(その2)


1. トラックという高価な設備の活用とは
2. 荷の積み降ろし
続きを読むには・・・
この記事の著者
合同会社Kein物流改善研究所
物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人...
この記事の著者
仙石 惠一
物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人材育成ならばお任せ下さい!
物流改革請負人の仙石惠一です。日本屈指の自動車サプライチェーン構築に長年に亘って携わって参りました。サプライチェーン効率化、物流管理技術導入、生産・物流人...
この連載の他の記事

現在記事
「サプライチェーンマネジメント」の他のキーワード解説記事
もっと見るセットメーカーのサプライチェーン経営課題
製造のサプライチェーンの中で完成品セットメーカーは、図1に示すようにアンカーです。 製造業において市場を支配するのは、通常プロセス上で最終組立を...
製造のサプライチェーンの中で完成品セットメーカーは、図1に示すようにアンカーです。 製造業において市場を支配するのは、通常プロセス上で最終組立を...
サプライチェーンマネジメントにおける自律分散と情報共有のインサイト
組織のマネジメントを「意思決定は自律分散的か中央集権的か」と、「情報の共有化がなされているか否か」との2つの視点によって分類してみましょう。 近代経...
組織のマネジメントを「意思決定は自律分散的か中央集権的か」と、「情報の共有化がなされているか否か」との2つの視点によって分類してみましょう。 近代経...
ギリギリまで作らない、運ばない、仕入れない (その5)
前回のその4に続いて、「ギリギリまでつくらない、運ばない、仕入れない」その5は、商品Noの統一、仕掛品Noの逆検索について、解説します。 ...
前回のその4に続いて、「ギリギリまでつくらない、運ばない、仕入れない」その5は、商品Noの統一、仕掛品Noの逆検索について、解説します。 ...
「サプライチェーンマネジメント」の活用事例
もっと見る実力把握は物流ベンチマーク活動で、物流サービスと物流コスト
1. ベンチマーク活動 ベンチマーク活動というものがあります。物流でいえばたとえば自社の物流コストが業界の中で競争力があるのかどうか...
1. ベンチマーク活動 ベンチマーク活動というものがあります。物流でいえばたとえば自社の物流コストが業界の中で競争力があるのかどうか...
現物在庫を見る:物流の改善ポイント(その2)
◆部品発注は物流現場で 在庫金額は小さくても、嵩が張るもので数量が大きいと在庫管理に苦労します。置ききれない在庫をあっちに持って行き、こっちに...
◆部品発注は物流現場で 在庫金額は小さくても、嵩が張るもので数量が大きいと在庫管理に苦労します。置ききれない在庫をあっちに持って行き、こっちに...
共同輸送への道筋 トラック積載率を上げるには(その1)
◆ 容器モジュールで物流改善 物流においてトラックの積載率を上げるように仕事を考えていくことは非常に重要です。トラックの能力を常に意識して仕事をし...
◆ 容器モジュールで物流改善 物流においてトラックの積載率を上げるように仕事を考えていくことは非常に重要です。トラックの能力を常に意識して仕事をし...