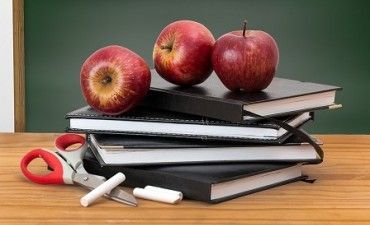TRIZとは、キーワードからわかりやすく解説
1. TRIZとは
TRIZとは、1940年代にロシアの発明家であり特許審査官でもあったゲンリッヒ・アルトシュラーが、多数の特許に触れるうちに一連のアイデア発想の共通点を見出し、それらを法則化してまとめたものです。 技術課題へのアイデアが出ない場合はもちろん、既にある場合でもより多くの良質なアイデアの中から選択する事で、開発設計の後戻りによる無駄を防止する事が可能となります。 旧来のTRIZは10個ほどのサブツールから成り立ち、必要なアイデアに応じて使い分けるのですが、現在ではそれらを包含した支援ソフトが発達しており、それらを使うのが一般的です。
2. TRIZの基礎概念
企業競争を勝ち抜くためには、他社よりも早くより良い答えにたどり着く必要があり、そのために自分たちの知識経験だけに頼っていては、その競争に遅れてしまいます。もしかしたら、他の業界ではすでに似たような問題を解決しているかもしれません。そこで、それを使わない手はないということです。すなわち、TRIZの基礎概念は、次の3本柱です。
- 技術システムの解決策は、分野を超えてパターン化できる。=発明原理
- 技術システムの進化の法則は、分野を超えて繰り返される。=技術進化のパターン
- 革新的な解決策は、他の分野の知識を活用して生まれた。 =科学的知識DB
TRIZは、ロシア語の「Τеория Решения Изобретательских Задач」(テオーリア・リシェーリア・イザブレタチェルスキフ・ザダーチ)の、頭文字をアルファベット表記したものです。これを英訳表記すると「Theory of Solving Inventive Problem」ですから、直訳すると「発明的問題解決の理論」となります。
3. TRIZで新商品を考える
TRIZの中にも新商品を考え出すための方法があります。対象がある程度見えている場合はTRIZで「なぜなぜ分析」等を用いて原因を追究し「やるべきこと」をはっきりさせることも可能です。また、TRIZの主要な構成要素の一つである「技術進化の法則」を利用し、対象とする技術が将来進化するであろう姿を予測する方法もあります。
TRIZを扱う方法の一つである「9画面法」を活用して、対象とする技術を「過去」から「現在」を経て「未来」を予測し、なおかつ対象技術を包含する技術システムを考えようとする方法もあります。これらの手法とマーケティング手法を組み合わせて用いられたりもしています。
これらは目的とする商品の狙い方や状況の捉え方によって差はあるものの、基本的には対象とするモノや技術に対して、現状の問題点を認識することから出発し、その問題を解決する新しい商品を考え出そうとするものです。
4. TRIZの具体的な主要ツール~問題解決の核 ~
TRIZの根幹をなすのが、発明のパターンを体系化した具体的な問題解決ツール群です。なかでも、技術的な「矛盾」を克服するためのアプローチは非常に重要です。
【矛盾マトリックスと40の発明原理 】
技術開発において、一つの特性を良くしようとすると、別の特性が悪化してしまうというトレードオフの関係、すなわち「技術的矛盾」に直面することがほとんどです。例えば、製品を「強く」しようとすれば「重く」なりがちで、「速く」しようとすれば「エネルギー消費」が増える、といった具合です。
TRIZでは、この技術的矛盾を体系的に解決するために、「矛盾マトリックス」と「40の発明原理」を用います。
矛盾マトリックスは、改善したい特性(39のパラメータ)と、悪化しても構わない特性(同じく39のパラメータ)を組み合わせた表です。このマトリックス上で、直面している矛盾の交差する箇所を参照すると、アルトシュラーが分析した特許から抽出された、矛盾を解消するために有効な40の発明原理の中から、推奨される原理が示されます。
この原理は、「分割」「統合」「局所化」「動的化」「汎用性」など、分野横断的な抽象的な解決策のヒントであり、具体的な技術アイデアそのものではありません。しかし、このヒントを基に、自分たちの専門分野に当てはめて発想を広げることで、過去の成功パターンに基づいた、より確度の高い革新的な解決策を導き出すことが可能になります。これは、闇雲にアイデア出しを行うよりも、効率的かつ効果的に矛盾を乗り越える手法と言えます。
【物質・場分析と76の標準解】
技術的な問題の中には、明確なトレードオフとして捉えにくい、複雑な物理的・化学的相互作用に関わる課題も多く存在します。このような問題を形式的に分析し、解決に導くのが「物質・場分析(サポール・ポレヴァヤ・モデル)」と、それに対応する「76の標準解」です。
物質・場分析は、技術システムを「物質(S)」「場(F)」「要素間の関係(相互作用)」という三つの基本要素でモデル化します。このモデルを用いることで、問題となっているシステムの構造や機能、あるいはその不足を明確に描き出すことができます。
システムのモデル化によって分類された問題のタイプ(例えば、有害な作用の除去、測定・検出の改善、システムの分解能向上など)に応じて、76の標準解が提供されます。これらの標準解は、物理法則や化学的知識を応用した抽象度の高い解決策であり、例えば、「システムに新しい物質や場を導入する」「相転移を利用する」「システムをマイクロレベルで変更する」といった具体的なアクションの方向性を示唆します。
矛盾マトリックスが技術的矛盾を打破するツールであるのに対し、物質・場分析と標準解は、システムの内部構造や相互作用に起因する問題を解決し、システムの機能を改善・進化させる強力な手法となります。
5. TRIZ導入の課題と成功へのポイント
TRIZは非常に強力な発想支援ツールですが、導入や活用には特有の課題があります。
一つの課題は、専門用語と概念の多さです。矛盾マトリックス、発明原理、進化の法則など、多くの専門用語を習得する必要があり、初期の学習コストが高いと感じられがちです。また、これらを使いこなすには、単なる暗記ではなく、問題の本質を「TRIZの言葉」に変換する抽象化能力が求められます。しかし、この抽象化こそがTRIZの最大の価値であり、成功の鍵となります。成功している組織では、まずトップダウンで導入の重要性を共有し、社内の特定のメンバーをTRIZの専門家(チャンピオン)として育成しています。
また、TRIZを単独で使うのではなく、既存の品質管理や問題解決の手法(QC、VE、シックスシグマなど)と組み合わせて活用することが重要です。例えば、問題の特定と原因分析には既存の手法を用い、革新的な解決アイデアの創出段階でTRIZを適用するといった、役割分担を行うことで、その効果を最大限に引き出すことができます。
TRIZは、天才の発明を再現するための「思考の技術」です。この技術を組織全体で共有し、継続的に活用していくことで、企業は他社にはない革新的な製品や技術をコンスタントに生み出すエンジンを獲得できるでしょう。
「TRIZ」のキーワード解説記事
もっと見るTRIZ 解説番外編、TRIZをタイタニックで学ぶ?【厳選記事紹介】
【目次】 TRIZは難しいという声を聞きます。そこで、ものづくりドットコム 登録専門家の粕谷 茂氏が、分かり易い事例からTRIZを紹...
【目次】 TRIZは難しいという声を聞きます。そこで、ものづくりドットコム 登録専門家の粕谷 茂氏が、分かり易い事例からTRIZを紹...
TRIZを使用したDFSS 【連載記事紹介】
TRIZ を使用した DFSSが無料でお読みいただけます! ◆TRIZとは ...
TRIZ を使用した DFSSが無料でお読みいただけます! ◆TRIZとは ...
QFD-TRIZ-TMの連携適用による開発事例【連載記事紹介】
QFD-TRIZ-TMの連携適用による開発事例が無料でお読みいただけます! ◆QFD-TRIZ-TMの連携適用による...
QFD-TRIZ-TMの連携適用による開発事例が無料でお読みいただけます! ◆QFD-TRIZ-TMの連携適用による...
「TRIZ」の活用事例
もっと見るQFD(品質機能展開)、TRIZ、タグチメソッドの融合について
▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデ...
▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に関するオンデ...
台湾・高機能ファブリックメーカーがTRIZで革新的課題解決
※写真はイメージです ♦ 市場をリードするイノベーション実現に向けアイデア発想力強化 1. 機能性ファブリック...
※写真はイメージです ♦ 市場をリードするイノベーション実現に向けアイデア発想力強化 1. 機能性ファブリック...
自動車部品メーカーの「待ち受け型から提案型製品開発」への転換~QFD-TRIZの活用
※画像はイメージです 今回はステアリングシャフトやドアヒンジなどの輸送用機器メーカーで2015年からTRIZを活用した技術課題解決力の強化、シーズ...
※画像はイメージです 今回はステアリングシャフトやドアヒンジなどの輸送用機器メーカーで2015年からTRIZを活用した技術課題解決力の強化、シーズ...
「TRIZ」の専門家
もっと見る「感動製品=TRIZ*潜在ニーズ*想い」実現のため差別化技術、自律人財を創出。 特に神奈川県中小企業には、企業の未病改善(KIP)活用で4回無料コンサルを...
片桐 朝彦
専門家A 株式会社アイデア
従来品の20%アップを目指すなら、今までのやり方で実現できるかもしれません。しかし、誰もが成し得なかったダントツ製品、ダントツ技術の開発を目指すとき、TR...
従来品の20%アップを目指すなら、今までのやり方で実現できるかもしれません。しかし、誰もが成し得なかったダントツ製品、ダントツ技術の開発を目指すとき、TR...