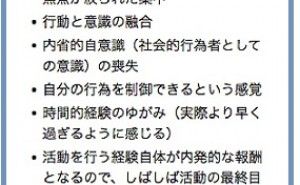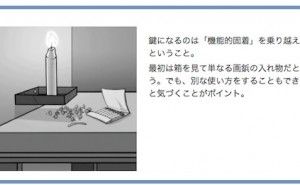1.グローバル化時代の人事制度
グローバル化が進むからこそ、日本の良さを前面に押し出した人事制度を創るべきです。なんでもかんでも欧米に見習えというのでは、日本の素晴らしさを消してしまうことになります。社員の能力を細かく分類して、賃金や賞与などの処遇にわずかな差をつけたところで、やる気が出る人は少数です。
ある研究期間の調査では、むしろ賃金格差をつけた方が、社員のやる気を阻害し、健康によくないという報告もあるぐらいです。バブル期以前に多くの日本企業が採用していたいわゆる能力主義は、高度経済成長時代には機能しましたが、現在の経営環境にはマッチしません。バブルが崩壊した直後に出てきた成果主義やコンピテンシーも多くの企業が取り入れましたが、弊害ばかりが目立ち、今ではほとんど語られることはありません。
今流行りのダイバーシティとかタレントマネジメントも同じような運命をたどると思っています。経営者はそんな風潮に流されず、日本企業の原点に立ち返り、その良さである助け合いや支え合いの精神、自分のことよりもまず組織を大切にすることが、自分自身の幸せにつながるという考え方を持つべきでしょう。
2.日本的な人事制度とは
簡単に言えば“ほぼ年功主義”です。ただし、年功の対象となるのは、全体の8割程度になります。ほとんどの社員は、皆同じように昇給や昇格をしていくという考え方です。年齢給、家族手当なども支給し、安心して働ける土壌を創ります。ただし管理職に登用することはなく、あくまでも一般社員として実務をこなす人たちが対象です。そして残りの2割の社員から、会社を引っ張っていくリーダーや特に優れたプレーヤーを抜擢します。年齢性別に関係なく、人物本位、成果本位でかまいません。当然、一般社員よりも厚く処遇します。ただし、社員のだれからも納得できるような人物を選ぶことが重要です。極端に言えば、評価で処遇に差をつける対象となるのは、そういう人たちだけで十分です。つまり“ほぼ年功主義”であって、年功だけで誰でも管理職になれるというわけではありません。
そしてもう一つ大切なことは終身雇用です。終身雇用は、生涯生活の不安を抱えずに生きていける、そのためにも自分が勤めている会社を守るという愛社精神を培うことができます。本人の意思と健康、それから周りの仲間の同意があれば、いわゆる定年もなく働けるような会社が理想です。長く働くことができれば、人生設計も楽になり、企業にとって、賃金カーブを調整しやすくなるというメリットもあります。例えば結婚して子育てが終わる55歳までは緩やかに昇給しますが、それ以降は、賃金を下げて、全体でバランスをとることも可能になります。
3.社員を大切にすれば人は育つ
フルコミッションのような販売会社なら別ですが、私自身が製造業のクライアントで実際にこの仕組みを導入してうまくいっていますので、問題はないと認識しています。クライアントの採用担当者から「頑張ればリターンがあるが、そうでなければ少...