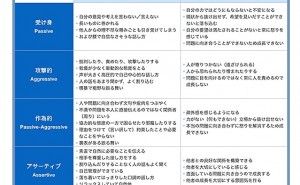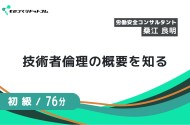1. 技術士試験でわかりやすい答案を書くためのポイント
【特集】技術士第二次試験対策:技術士第二次試験に関する記事まとめページはこちら!口頭試験や論文対策などのポイントについての記事を紹介しています。
頭の中の交通整理をすることでわかりやすい答案を書くことができます。頭の中の交通整理とは、「『解答すべきことの要点』と『解答すべきことの要点に関する説明』を考えること」です。次に、考えたことを答案用紙に書けばわかりやすい答案を書くことができます。
わかりやすい答案(試験官に解答が明確に伝わる答案)を書くための重要なポイントとは以下の2項目です。
◆解答すべきことの要点を考える(解答を簡潔に言ったことを考える)
◆解答すべきことの要点に関する説明を考える
ここで、試験の解答内容を1本の木と考えたとします。解答すべきことの要点とは、この木の“幹(解答の幹)”です。解答すべきことの要点に関する説明とは、この木の“枝葉(解答の枝葉)”です。
以下の問題と解答例を読んでください。解答例の中で、赤い字の箇所が解答の幹です。茶色の字の箇所が解答の枝葉です。
【問題】
地球温暖化の原因の1つとして二酸化炭素の増加があります。あなたが考える二酸化炭素の増加を防ぐ対策を書きなさい。
【解答例】
私が考える対策とは、家庭でできる取り組みを行うことです。具体的には、以下のような対策を行うことです。
(1) 冷房の設定温度を1℃高く、暖房の設定温度を1℃低く設定する。
(2) 風呂の残り湯を洗濯に使う。
(3) 買い物に行くときには買い物袋を持参する。
このように、わかりやすい答案での解答内容は、“解答の幹”と“解答の枝葉”で構成されています。このことから、わかりやすい答案を書くための重要なポイントとは、「解答の幹と解答の枝葉を考えること」と言い換えることができます。
2. 解答の幹と解答の枝葉を考えること
2.1 「解答の幹と解答の枝葉を考えること」に慣れる
試験場で問題を読んだら解答の幹と解答の枝葉を考えてください。この解答の幹と解答の枝葉を答案用紙に書くことでわかりやすい答案が書けます。「解答の幹と解答の枝葉を考えること」に慣れてください。これに慣れることで、試験場で、わかりやすい答案を書くことができます。
2.2 トレーニングの方法
「解答の幹と解答の枝葉を考えること」に慣れるためのトレーニングの方法を解説します。
受験勉強時にこのトレーニングをすることが基本です。しかし、このトレーニングの特徴は、日常業務の中でもトレーニングができることです。その1つとして、文書を書くときにトレーニングをする方法を解説します。
文書を書くときには、以下のように考えます。
◆解答すべきことの要点を考える(解答の幹)=伝えたいことの要点を考える(伝えたいことの幹)
◆解答すべきことの要点に関する説明を考える(解答の枝葉)=伝えたいことの要点に関する説明を考える(伝えたいことの枝葉)
トレーニングの対象とする文書は何でもかまいません。業務報告書、技術提案書あるいはメールを書くときなどでもかまいません。例えば、メールを書くときを考えてみます。
上司に、A社に提出する技術提案書の作成の進捗状況を説明するメールを送ることを考えてください。「伝えたいことの幹と伝えたいことの枝葉を考えること」を使ってメールを書くと、例えば、以下のような内容のメールになります。
『A社に提出する技術提案書はまだ完成していません。◯月◯日の17時までには完成させます。当初、△月△日の17時までには技術提案書を完成させる予定でした。しかし、技術提案書(提案内容)が確実に採用されるためには提案内容を一部修正したほうがよいと判断しました。』
メールの中で、赤い字の箇所が伝えたいことの幹です。茶色の字の箇所が伝えたいことの枝葉です。このようにメールを書くことで、わかりやすいメールを書くことができます。
他の文書でも「伝えたいことの幹と伝えたいことの枝葉を考えること」に基づきわかりやすい文書(読み手に内容が明確に伝わる文書)を書いてください。これを日々実践することで、「幹・枝葉」を考えることに慣れ、試験場で、わかりやすい答案が書けます。
また、この「幹・枝葉」を考えるこ...