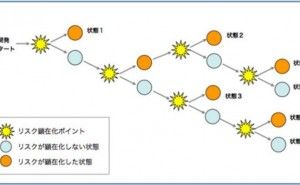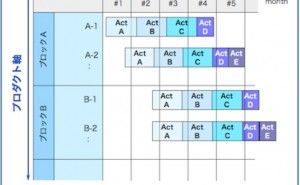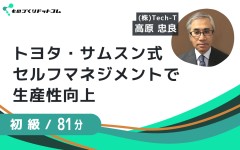今回は、マクロ的な視点でみた
イノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。
東西冷戦の終結を機に加速した経済のグローバル化は、かつての先進国中心の世界経済から、新興国の台頭による市場の多極化をもたらし、世界経済の景観を一変させました。また、同時に国という枠を超え、国家と匹敵する経済規模をもったグローバル企業を生み出し、国と企業の利益が相反する状況も生まれました。
一方、一人ひとりの生活者は、自分の住む国や地域に根差した存在であり、経済格差の拡大を背景として高まったグローバリゼーションへの違和感を、民衆の意志として示し始めているように感じます。今後、グローバリゼーションという流れが具体的にどのように変化していくのか、先読みすることはなかなか難しいのですが、マスメディアや評論家の得意な「グローバリゼーションか、反グローバリゼーションか」といったわかりやすい二項対立ではなく、2つの要素が絡み合うなかで、次の時代の経済のありかた、人々の生活のあり方、そして企業のあり方への模索が繰り返され、積み上げられていくものと考えます。
実際、グローバルにビジネスを展開しながらも、それぞれの国と地域に根差した企業市民として根付き、信頼を獲得している企業も多くあり、グローバリゼーション自体が問題の本質であるとは思えません。単に自らの利益のみを中心に捉え、グローバル化の流れに乗るのか、「グローバリゼーションの本質はローカリゼーションにあり」として、グルーバルにビジネスを展開しつつも、それぞれの国と地域に貢献する企業市民となるのか、これからの時代、個々の企業の生き方が一層問われくるものと思います。
いずれにしても、もうひとつの潮流であるイノベーションへの挑戦は、国、企業、地域さらには個人を含めた様々な次元でますます加速してくものと思います。イノベーションの本質は、「顧客価値の創造と具現化」であり、一人ひとりの生活者にベネフィットをもたらすものであり、国及び地域の経済成長の原動力だからです。
経済理論によれば、国の経済成長は、働く人の労働時間の増加と労働生産性の向上により実現されるといいます。日本のような先進国の多くは、少子高齢化に伴う労働人口の減少が課題になっています。安定的・持続的な経済成長を実現していくためには、定年の延長による高齢者の活用、女性が活躍し続けられる社会環境づくりなどの労働時間の増加を促す取り組みに加えて、労働生産性を向上させていくことがますます重要になります。期せずして、IoT、ロボット、AIなどの労働生産性の飛躍的な向上を実現する可能性を秘めた技術が萌芽期から実用段階へ移行しつつあり、これらの技術の研究と実用化は、国の経済政策・科学技術政策の柱となっています。かつては、経済成長を維持するためには、移民の受け入れ拡大が必要だといった議論もかなり見られましたが、グローバリゼーションの流れに変化が生じる中、国外からの労働力の導入よりも、生産性の向上の重要性が...
 今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。
今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。 今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。
今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。 今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。
今回は、マクロ的な視点でみたイノベーションの意味について、解説します。2016年は、グローバリゼーションに対する変化が顕在化した年でした。イギリスのEU脱退やアメリカのトランプ大統領の誕生などは、その象徴的な例だと思います。