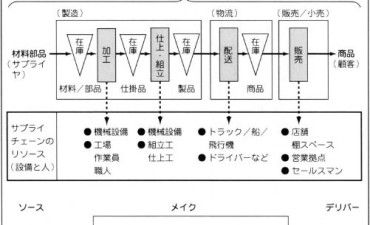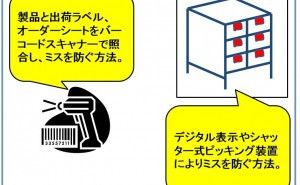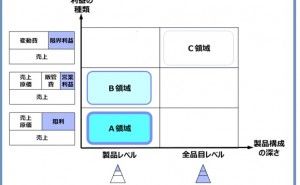1.機密保持契約とは
◆ 秘密は文書、データ、口頭情報にも含まれる
物流に限らず、すべての事業を行う際に重要になってくるのが「契約」です。当たり前のことと思われがちですが、意外としっかりとした契約書を取り交わしている会社は多くないかもしれません。そこで今一度、物流ビジネスの契約について考えてみたいと思います。
契約を開始する際、真っ先に結ぶと思われるのが「機密保持契約」ではないでしょうか。当事者間で取り交わすさまざまな情報について、外部に漏らさない約束をするのがこの契約の目的です。では、どこまでの情報が機密に当たるのでしょうか。一般的に契約を結んだ際、すでに公知のものとなっている情報は機密情報とは扱われません。
基本的に相手側に開示した情報はすべて機密情報と考えたいところでしょうが、何でもかんでもとなると、実際にその情報管理上の課題があるでしょうから、一定の線引きをした方がよいと思われます。お互いに「機密情報」と明示したものだけを特別の管理とした方が効率的です。そして文書であれ電子データであれ、そのどこかに「秘密」という表示をすることです。
当然のことですが、会話の中にも機密情報が含まれていることがあります。つまり、その場で消えてなくなってしまう口頭情報にも「秘密」は含まれているのです。ではその扱いはどうしたらよいでしょうか。会話をする際に「この話は秘密だけど」と、前置きしてから話を始める必要があります。
「『秘密』と明示した文書およびデータ、会話の際に『秘密』と前置きされた情報については特別な管理を行う」といった主旨の文言を機密保持契約書に記せばよいのです。そしてこれらの情報は、当事者どちらかから返還要請があった場合は、速やかに返還する旨を取り決めておくことが大切です。
また機密保持の期間ですが、仕事をしている期間は当然として、多くの契約で契約期間が終了した後でも、機密保持を守らなければならないと取り決めているケースが多いようです。機密情報に無頓(とん)着な人がいるようですが、ビジネスにおいて相手方の情報を漏えいしないということは当たり前のことです。ついつい、しゃべりたくなってしまうこともあるかもしれませんが、社内教育をしっかりと行い情報管理を徹底させましょう。
2.契約書記述事項とは
◆ 契約書に記すべき業務とは
契約を曖昧にしていると、実業務が始まった後にトラブルが発生しがちです。しかし、そのトラブルのもとになる事象は大抵が想定の範囲内です。これは何を示しているのでしょうか。それは契約書を作る際、真剣に考えていないということが考えられます。または、契約書作成に慣れていないといった方がよいかもしれません。契約書は誰が作るのでしょうか。営業担当者が作るのでしょうか、それとも法務担当者でしょうか。
大きな会社であれば法務担当部門があり、契約書管理を一手に引き受けています。この場合、リーガル的な観点からは問題が無い契約書を作っています。しかしリーガル的観点以外の所が重要なのです。つまり本来発注すべき仕事、受注した仕事といった「何を」仕事として実施すべきかについての観点が外せないのです。
「何を当たり前な」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし意外と契約書に書かれていないものの、実際にはやられている業務が存在するものです。しかも受注側がこういった業務を「無償」で実施している場合があるのです。例えば、契約後に契約書に書かれた仕事以外で、次のような業務が発生していることがあります。
- 在庫数量の日々報告
- 通箱数量の報告
- 通箱の清掃
これらにつきましては、物流業務を行っていれば当たり前に発生が予測される仕事です。しかしこれらを契約書に書くかどうかは別として、発生を予測し、あらかじめ価格に織り込んでおかないと、後で大変なことになりがちです。どうしても顧客に頼まれれば断れず、簡単に引き受けてしまいがちです。しかも無償でです。一つひとつの仕事は小さくても、そういった業務が増えてくる、あるいはその仕事のボリュームが大きくなると無視できない存在になります。
そこで契約前に、まずは予測される業務を洗い出し、それを列挙しておくことが求められるのです。顧客側もすべての顧客が、自社の発注業務を100%把握できているとは限りません。できれば事業者側で列挙した内容を顧客に提示し、契約書外業務発生の可能性について話し合っておくことがよいと思います。

3.損害賠償の範囲とは
◆ 荷物の延着や損傷など、想定される事象は契約書に!
物流で扱う他人からの預かりものに対しては、十分に注意して取り扱うことが求められます。物流の過程で顧客の荷物を損傷してしまった場合には賠償責任が生じます。この損害賠償の範囲をどこまでにするのかは契約で決まります。この場合「物流受託者側の責任で、荷物を損傷したケースにおいて賠償を行う」という文言になると思われます。
では、交通事故で道路が大渋滞し、延着が発生した場合にはどうなるでしょうか。常識的に考えれば不可避的事項として免責としたいところです。しかしこういったケースを想定し、契約で決めておかないと事業者責任を求められることにもなり兼ねません。
冬場の大雪で道路状況が極めて悪い時に「何としても着けろ」という指示が、荷主から出ていたという話を聞きました。これは一種の天災にあたる可能性がありますが、やはり契約書に何かしらの文言で記しておく必要がありそうです。こういった延着の事由はある程度想定されますので、それを契約書に入れておくことは難しいことではありません。
顧客の荷...