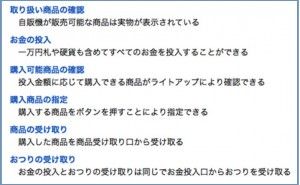本業であるフィルム事業がなくなることを経験した、富士フィルムの技術の棚卸活動は注目に値します。アスタリフトや液晶用フィルムは、フィルム事業で培ったコア技術が中核にありました。 今回は、アスタリフト事業に見るコア技術の活用戦略を見てみます。
コア技術の可視化をした上でなすべきは、「何に使えるのか?」を検討することです。フィルムのコラーゲン技術を活かしたアスタリフトは、大きくはないものの、事業として成立しています。文献や証拠はありませんが、このアスタリフトの事業化の経緯は、「コラーゲン技術の有効活用」という意思にあると見ています。
富士フィルムの研究開発の方針では、次のように新規事業開拓と既存事業の成長という2つが示され、事業と研究開発の密接な関連性が謳われています。
- 1. 生活の質の向上に貢献できる骨太の新規事業開拓
- 2. 革新的新製品による既存事業分野の成長持続
また5大方針には、「複数の異種技術融合による新たな価値創造」が記載されています。技術が強い部分で新規事業に結びつけるアプローチはキヤノンでも同じです。これは、コア技術を継続的な競争力に結びつける考え方に由来します。
コア技術が継続的な競争力に結びつくために、単なる研究開発だけで足りないことは、DVDやカーナビ等の事業の歴史が証明しています。富士フィルムでは、ヘルスケア市場にコア技術を活かすための活動が行われたと説明されています。
研究者として、アスタリフトの開発に関わった田代氏は次のように述べています。
「ヘルスケア分野へ市場参入した当時は、アミノ酸の培養技術を生かして肌にとって適した量のアミノ酸を配合した化粧水を開発していました。一方で、富士フイルムの特長をもっと生かした化粧品の開発をしていきたいな、という思いは以前からあったんです。 肌にとって何が必要かと考えたとき、シミやシワといった女性が本当に気になる部分をフォローする化粧品を開発しなければならないと当時から考えていました」(出典:富士フィルムホームページ)
肌の本質を考えた時に、「コラーゲンが使えるではないか」、という仮説があったのだとここから理解できます。下線部が「思い」と説明されていますが、会社から...