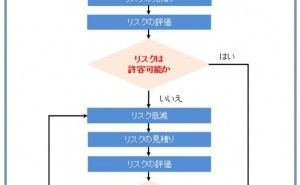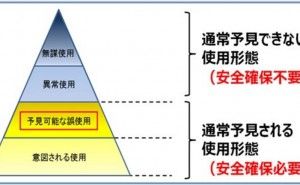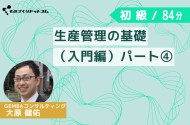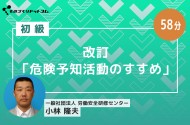「予知保全」とは、設備や機械の故障を未然に防ぐための手法であり、近年、技術の進化とともにその重要性が増しています。従来の保全手法は、故障が発生した後に対応する「事後保全」や、定期的に点検を行う「定期保全」が主流でしたが、予知保全はデータ分析やセンサー技術を活用し、故障の兆候を早期に発見することを目的としています。この新しいアプローチは、製造業やインフラ管理など、さまざまな分野での効率化やコスト削減に寄与しています。
さらに、予知保全は安全工学とも密接に関連しており、事故やトラブルを未然に防ぐための重要な手段となっています。これからの時代、AIやIoT(モノのインターネット)などの先進技術が予知保全の実現を加速させており、私たちの生活や産業に大きな影響を与えることが期待されています。今回は、予知保全の基本概念からその新時代の展望、安全工学との関係性までを分かりやすく解説していきます。
1. 予知保全とは?予知保全の重要性
予知保全(Predictive Maintenance)とは、設備や機械の故障を未然に防ぐために、データ分析やセンサー技術を活用して、状態を監視し、必要なメンテナンスを予測する手法です。従来の保全方法である定期保全や事後保全に比べて、より効率的で効果的なアプローチとされています。予知保全の重要性は、主に次の点にあります。
【予知保全の重要性】
- ① 故障の予測が可能になる・・・・・・・予知保全で計画的なメンテナンスが行えるため、突発的なダウンタイムを減少させることができます。これにより、生産性が向上し、コスト削減にもつながります。また、設備の寿命を延ばすことができるため、長期的な投資効果も期待できます。
- ②データに基づいた意思決定が可能になる・・・・・・予知保全は、メンテナンスの効率が向上します。例えば、どの部品がいつ劣化するかを予測することで、必要な部品だけを事前に準備し、無駄な在庫を減らすことができます。これにより、資源の最適化が図れます。
- ③安全性の向上・・・・・・・予知保全は安全性の向上にも寄与します。故障による事故やトラブルを未然に防ぐことで、作業環境をより安全に保つことができます。このように、予知保全は企業にとって非常に重要な戦略であり、今後ますますその重要性が増していくと考えられています。
(1)予知保全と予防保全との違い
従来の保全(予防保全)は、設備や機械の定期的な点検やメンテナンスを行う方法です。例えば、一定の時間や使用回数に基づいて部品を交換したり、オイルを注入したりします。この方法は、故障が発生する前に予防的に対策を講じることを目的としていますが、実際には必要のないメンテナンスを行うこともあり、コストや時間の無駄が生じることがあります。一方、予知保全は、データ分析やセンサー技術を活用して、設備の状態をリアルタイムで監視し、故障の兆候を早期に発見する手法です。これにより、必要な時にだけメンテナンスを行うことができ、無駄な作業を減らすことが可能です。例えば、振動や温度、音などのデータを収集し、異常が発生する前に対策を講じるこ...