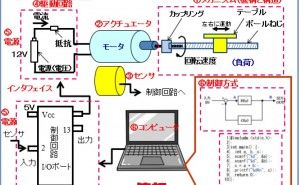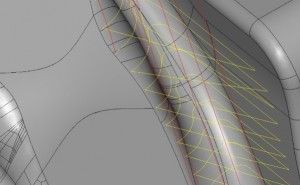エネルギーや資源に乏しい我が国では、省エネ省資源の新材料や製造プロセスの技術革新が求められています。例えば固体表面に液滴が付着すると、表面の腐食や劣化、外観の悪化、流体抵抗の増加などの原因となり、装置・機器の安全性や信頼性を損なうことから、液滴除去性能、付着防止に優れた表面処理技術が求められます。既存の液滴除去、付着防止のための表面処理技術である表面の微細加工、有機フッ素化合物による表面処理に加えて、技術革新の観点からさまざまなアプローチによる開発が行われています。
このように部品・製品には多種多様な表面処理が施されていますが、その目的は、電気的特性、光学的特性など基材と異なる機能の追加、低摩擦や耐食性向上など基材の保護、機能向上などです。
自動車の軽量化や電子機器の小型化の流れで、部品への要求は厳しさを増しています。低コスト化の観点から必要な箇所のみに処理を施すことで目的を達成する表面処理技術が期待されています。
今回は、このような背景を踏まえて、表面処理の概要を解説します。
1. 表面処理とは
表面処理には2つの流れがあります。表面処理を機械加工の前に行なうのをプレコート、機械加工の後に行うのをポストコートと呼んで、このプレコート、ポストコートの2分類が表面処理の流れです。
表面処理鋼板ではコストで有利な為、プレコートが増えています。表面処理鋼板の長所と短所ですが、長所は、高い生産性、均一な皮膜、均一な皮膜厚です。短所は、プレス加工性、連続溶接打点性、端面耐食性が悪いなどです。
2. 表面処理技術の概要
表面処理で良い特性が得られるとしても、対象物との相性が悪く、使用環境・使用条件に適合していなければ、表面処理効果は半減してしまいます。製品・部品の寸法、形状、作業工程の変更、それを構成している材質の変更が求められるなど、製品・部品がそのままの状態で表面処理ができるとは限りません。
表面処理による表面の改質には、付加加工と除去加工の2つがあります。付加加工は、除去加工以外の表面処理で、表面処理の本質です。除去加工は、表面付着物、もしくは材料そのものを削る処理方法です。表面の改質現象の違いで付加加工は次のように分類できます。
【付加加工で表面の改質現象の違いによる分類】
(1)他元素を染み込ませる加工
浸炭処理・窒化処理などです。熱拡散によって他元素が表面から染み込む表面処理です。基材との境界はありません。
(2)他の物質を載せる加工
多くの種類の表面処理で、塗装・めっき・ライニングなどです。表面に基材とは異なる処理層を形成します。境界が明確です。
(3)化学反応させる加工
化成処理・陽極酸化などです。化成処理で得られるリン酸亜鉛層は、塗装下地、塑性加工時の潤滑、防錆の効果があります。アルミニウムを陽極酸化した場合、表面にアルミニウム酸化物層を作り、耐食性、耐摩耗性が向上します。
(4)他物質を載せ、基材境界に元素を染み込ませる加工
溶融亜鉛めっきなどが該当します。純亜鉛によって形成された最表層下に、鉄と亜鉛の合金層が出来ます。熱CVD・溶融亜鉛めっきです。
(5)表面化学成分はそのままで、金属組織が変わる加工
表面を急速加熱・急速冷却するだけで、表面組成は変化しません。一方、表面の金属組織は焼入硬化するため、耐疲労性・耐摩耗性は向上します。高周波焼入れ・炎焼入れなどの表面焼入れが該当します。
3. 表面処理と金属製品
(1)金属製品における腐食現象
腐食は、湿食と乾食があります。湿食は水によって生じる腐食で、さまざまな腐食形態があります。乾食は、高温によって生じる腐食です。酸素を含む気体中で加熱されたときに生じる酸化と、反応性ガス中で加熱したときに生じる腐食があります。防止には材料選定...