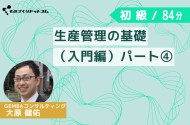1. サプライチェーン・マネジメントの狙い
サプライチェーンマネジメント(Supply Chain Management・以下SCM)は、ITシステムやネットワークを駆使し、精密な需要予測から生産計画にタイムリーに反映させ、企業や取引先、仕入先を含めた企業集団の経営効率を高めようとするものです。具体的には、店頭の販売現場情報を基に、在庫圧縮や納期短縮などを進め「売れる量だけ調達し生産・販売する」という仕組を組み立てます。SCMには視点や立場の違いから、いくつかの解釈と定義がありますがサプライチェーンについては共通しています。
サプライチェーンとは、資材の調達から生産、輸送、販売を通じて最終顧客に至るまでの流れのことで、これを一つの連鎖としてとらえ、プロセスの無駄を削減しながら統合的に管理するのがSCMの狙いです。
2. SCMの背景
多くの企業ではBPR(Business Process Re-engineering;業務プロセスの抜本的改革)やERP(Enterprise Resource Planning;統合資源管理)など企業内の業務プロセスの改革にこれまで取組んできましたが、企業内の活動だけでは限界があることが分かってきました。例えば、市場における需要と供給の間には常にアンマッチがあります。これを解消し、在庫や欠品をゼロにするには一企業の努力だけでは難しく、市場に向けて連鎖する企業間の商品の流れ、つまりサプライチェーンを短くし、フレキシビリティを高めていかなければなりません。また、企業と企業の間には壁があるために様々な無駄が発生しています。例えば、手続きの違いによるやり直しの無駄や、各種書類が標準化されていないために転記作業が発生したり、さらには機能自体が重複していることも見受けられます。これらを統合的に整理し、最適化を追求することでサプライチェーン全体の効率化を図ろうという動きが活発になってきています。
3. SCMの効果
(1)売上の増大
売上を増大させるためには、製品や商品をより多くの顧客に、より多く・より高頻度に買ってもらうことが必要です。SCMの観点からは以下のように大きな効果が期待できます。
- 需要動向をクィックに反映し、顧客の求めるもの=売れるものの欠品を起こすことなく継続的に供給する。
- 顧客サービスを向上させ、より多くの受注につなげる。
(2)在庫の圧縮
SCMを実施すると、各サプライチェーンの在庫が取引先同士で把握できるようになり、メーカー・卸・小売などの各社が余分な在庫を保持することなく、消費者の需要に応じて対応することが可能になります。また、小売店が提供するPOSデータから需要予測を行うことで、生産や配送などの効率化が可能になり、市場の変化に最小限の在庫で対応できるようになるわけです。在庫コストの削減は、サプライチェーン各社にとって大きな利益をもたらします。
(3)資産・設備の圧縮
資産・設備をより有効的に活用することができれば、需要が増大したり、生産の波が発生しても、追加設備投資をすることなく既存の資産や設備のままで、より大きなアウトプットを導き出せるようになります
(4)コストの削減
サプライチェーンでのムダを発見し、排除することが出来れば、サプライチェーン上の各種活動に関わるコストを削減できます。上流工程で発生した変動は下流工程で吸収しなければならず、残業や休日出勤を余儀なくされますが、SCMにおいては工程各社の生産計画をきちんと同期化し、納期を満たしかつ、無駄な仕掛かりを発生させないように情報システムでコントロールします。
(5)配送費用の削減
SCMの高度な利用が可能となると、顧客に回答する納期は、憶測でなく「確実な」ものとなり、関連する各社や物流業者との計画とも同期がとれるようになります。このため「納期直前になって高価な配送手段を用いて何とか納期を遵守する」といった必要がなくなり、配送費用が低減します。
(6)納期の短縮
SCMにより物や情報の流れがスムースになり、原材料の調達から商品が消費者に届くまでのリードタイムが短縮されます。リードタイムが短縮されるということは、お客様の満足度を向上させるだけでなく、原材料などの資材...