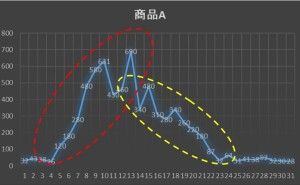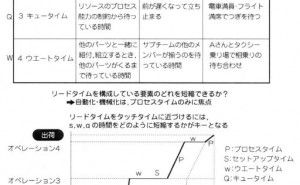◆ 物流共同化の意義とネック
共同物流は複数のユーザーがお互い協力し合い、一緒に物流活動を行っていくことを指します。輸配送の共同化や容器、パレットの共同化などが真っ先に頭に浮かぶアイテムでしょう。
最近、この物流の共同化を進めていく意義が一層明確になってきました。その一つがドライバー不足です。今やトラックドライバーを含む運転職の求人倍率は2倍を超えてきています。若者はクルマを持ちたがりません。一昔前はクルマを持って色々な所に出かけていくことがレジャーの中心でした。しかし免許を取らない若者も増えてきています。
このような状況下、トッラクドライバーの成り手は激減しています。特に大型トラックを運転するための大型免許を取る若者などほとんどいない実態にあります。現時点で大型トラックで当たり前のようにモノが運べている会社も、いずれ運べない状況がやってくる可能性も増してきているのです。
お互いにトラックを共同で使う、つまり混載を実施したり、行き帰りを融通しあったりすることで、将来的な輸送力不足に対応するニーズが出始めているのです。さらなる市場競争の激化も共同化を後押ししています。各社は自社製品を作って売るわけですが、人口減少時代に入った昨今では供給が過剰な状態に入った業種も出てきています。
競争に勝つためにはより良い品質の商品をより短納期で、より低価格で提供する必要性が出てきています。そのためにはコストも下げていかなければなりませんが、物流コストもその例外ではありません。物流コストを下げるためには共同物流が効果的なわけです。しかしながらこの共同物流ですが、それほど成功事例は多くありません。それは何故でしょうか。
一つに企業が未だ物流でも競争すべきと考えていることが挙げられます。人口減少のこの時代にあっては製品では競争しても、物流では協調すべきなのですが。
もう一つに秘匿情報の流出リスクが挙げられます。他社と物流で共同活動を行うと、今まで表に出せなかった情報を出さざるを得ない場合が出てき...